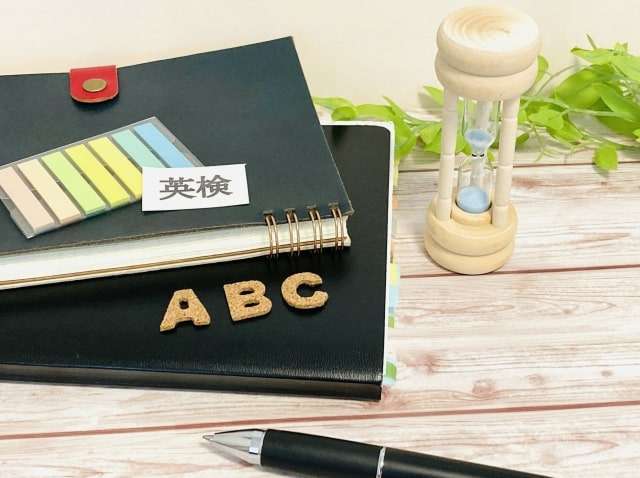オーストラリア式英語教育の意味と可能性
2023/06/10
※2024年2月1日 更新しました。
オーストラリア式英語教育
英語教育の改善に向けて
1.オーストラリア式英語教育が教えてくれるもの
A. 弊社のオンライン英語講座の取り組みについて
以前にオーストラリアに2年ほど住み、英語を使って生活したことのある日本人の方から、弊社のオンライン英語講座に関する問い合わせをいただきました。それによると、自分の知り合いに英語が全くできない人がいるので、その人にネイティブの講師の授業を受けさせたいが、可能か、というものでした。それに対して、英語が全くできない人の場合、ネイティブの講師の英語があまりよく聞き取れない恐れがあります、と問題点を伝えると、「それについては、私もその方と一緒に授業を受け、必要なとき、私が通訳します。」という答えが返ってきました。なるほど、それなら英語初心者でもネイティブの講師の授業を受けることができるかもしれないと思いましたが、それに関連する別の問題が気になったので、重ねて次のように尋ねました。「分かりました。あなたがその方と一緒に授業を受け、講師の英語を通訳していただければ、その方は安心して授業が受けられます。でも、そうなると、あなたのことが気がかりです。お見受けしたところ、あなたの英語力は多分中級以上でしょうから、初級者を対象に開講されるその授業はあなたにとっては易し過ぎて、学ぶ事はほとんどなく、むしろ退屈でしょう。すると、不満が溜まってくるのではありませんか?」この質問に対して、すぐに次のような返事が返ってきました。「いいえ、そんなことはありません。なぜなら、私はもうかなり長い間海外に行っていないので、ネイティブの講師と英語で話ができるだけで、リスニングとスピーキングの練習になります。私にはそれで十分です。」
これには私もびっくりしました。最初のうちは、「初心者に英語ネイティブの講師?何言ってるの?冷やかしのつもり?」などと勝手に思いを巡らせ、軽くあしらうつもりでいたので、受け入れ担当者として言うべきことはきっぱりと言い、その上で先方の言い分も聞いてみたのですが、不思議や不思議、その答えには何の力みも感じられず、自然体で、話の辻褄も見事に合っていたので、むしろ感心しました。しかしその一方で、私はかつて経験したことのないほどの厳しい挑戦を感じました。一見簡単に見える要望の彼方に教育の無限の可能性が垣間見える反面、空恐ろしいほどの難問を抱え込んでしまったとも感じたのです。私の直感は、「これは相当危ない。この先、とんでもない落とし穴が待ち構えているかもしれないぞ」と、私に警告を発していました。
でも、ここまで話を聞かれた皆さんの中に「おや、随分と変わった提案ですね。前代未聞かも。でも、肝心なのは本人ですよ。その方が望んでいらっしゃるのなら問題ないはずです。一体、何を迷っているんですか。」と思われた方はいらっしゃいませんか。もしいらっしゃったら、ある重要なポイントが思考の枠組みから抜け落ちている恐れがあります。「えっ、何のこと?」と思われた方がいらっしゃるといけないので、今回の「要望」の中身が、これまで表に現れてこなかった箇所も、一つ一つ反転させることで、一全体像としてくっきりと浮かび上がるように記述しておきます。
《ある町に、英語が全くできない人が住んでいます。また別の町に、海外で2年ほど英語を使って暮らしたことのある人が住んでいます。この二人は中年の社会人で互いに知り合いです。そして二人とも英語の運用力をさらに向上させたいと思っています。そこで、弊社から、この両者(=一方は英語初級の学びを、もう一方は英語中~上級の学びを期待するものと推察される)にリモートで、二人に特化した英語授業を提供してもらいたい。その際、担当の講師は、二人の英語力の差を正確に把握した上で、同一の授業に二人を迎え入れ、二人を同時に教え、二人に同等の気配りをしながら、それぞれの英語力を大きく伸ばす工夫をし、二人の学習意欲をも、個々にしっかり満足させてもらいたい。なお、授業は英語ネイティブの講師に英語のみを使ってやっていただきたい。》
いかがですか。私が「同一の授業に二人を迎え入れ、二人を同時に教え・・・」などと要望の中身を構成するポイントを、洗いざらい、赤裸々に、反転させたことで明白になったように、この問い合わせの要点は、到達レベルのはっきり異なる二人の英語学習者を、同一の授業の中で、英語学習における二人の異なる学習目標を常に念頭に置きながら両者を教え、二人それぞれに学習の成果を治めさせてほしい、という極めて高度な要望にあったのであり、有体に言えば、ほとんど無理難題に近い要求の押し付けにあったのです。さらに重ねて言えば、二人の受講希望者が達している英語学習における異なる到達度を一旦不問に付し、二人に対して同一の授業を実施する用意が弊社にあることが、この二人が弊社の講座に受講を申し込む際の条件だったのです。そして、この点にこそ根本的に重要な、また極めて深刻でもある、問題が隠れているのです。なぜなら、もしも弊社が、そして授業者が、深く考えもせずにこの要望を受け入れるなら、支離滅裂で中途半端な、そしてそれ故に、恐ろしく出来のよくない授業を提供するか、あるいは、一方の受講者にのみきちんとした授業をし、もう一人は容赦なく切り捨てる非情な授業をするかのどちらかにならざるを得ないからです。どちらの場合も決して望ましい結果にはなりません。敢えて強行すれば、教育の公正さを著しく欠くことになるからです。
ただし弊社は、今回この「要望」を寄せられた方が弊社を困らせるために無理難題を言ってきたと、「下衆の勘繰り」をしたわけではありません。むしろそのような意図はなかったと考えています。けれども、現実には今申し上げたような事態を引き起こす可能性が極めて高く、今回の要請は、少なくとも意図せざる波乱要因を内包しているのです。ですから、大局的に見て、問題はむしろ弊社の対応にあると見るのが正しいのです。今回の「問い合わせ」に含まれている教育上の問題点を理解し、その危険性を十分認識したうえで、弊社として、果たして「要望」を受けいれるのか、それともきっぱりお断りするのかが問われているのです。言い換えれば、予想される危険性をしっかり視野に入れた上でのリスク管理の仕方と問題が生じた際の社会的責任の取り方が問われているのです。つまり、この要請に応じた場合に、かなり高い確率で受講者が蒙るはずの深刻なダメージへの十分な対応策が、果たして弊社に用意されているかどうかの問題なのです。
ここで一つ、皆さんにお伺いしておきます。このような授業を、一体どこの国の、どの英語ネイティブ講師が、好き好んで引き受けるでしょうか?答えは言うまでもなく否です。そのような授業を引き受けるには、リスクが大きすぎるからです。そこで弊社がどのように対応したかは、この後すぐに述べるとして、その前に、一般論としての正統的、かつ合理的な対応をまず述べさせていただくなら、学校でも塾でも、このような二人は、習熟度別のクラスに振り分けて対応します。個別指導塾では、個別に対応します。このいずれかの措置をとるための条件がそろっている限り、誰もこれ以外の対応をとることは考えられません。
B. 英語初級と英語中級の平均学力差について
ところで私は、これまで、異なる到達度とか学力の差という言葉を、さも当たり前のように使ってきましたが、現実に即して言えば、英語学習においては、日本人の場合、中学1年生の後半ごろから徐々に、例えば、期末試験の得点差などの形で、個人間の学力差が目立ち始め、中学3年になると差がさらに大きくなります。高校、大学と進むと、その差はますます一方的に広がり、社会人では、英語の初級者と中級者、あるいは中級者と上級者の間には、教育環境、本人の努力などの様々な要因が重なった結果、英語運用能力に関して言えば、すでに途方もなく大きな差が現実に存在します。
英語は義務教育の小学校高学年から教科化されており、それは中学まで続きます。さらに日本国民の九割以上が高校に進学する現代の日本においては、事実上高校までが義務教育と考えてもおかしくない状況が存在します。ところが、明治以来、日本では英語力は英文を読んだり書いたりする力の養成に力を注ぎ過ぎてきたため、オールラウンドな英語運用の力の養成がおろそかになってきました。したがって、日本人一般における英語運用能力の低迷が今でも続いています。しかし真の英語力とは英語運用能力のことです。聞く、話す、読む、書く、の四技能の偏らない養成が英語力の養成であることは誰も否定できません。そこで、英語学習の成果の度合いを、この線に沿って見直す必要があります。ですから私の提案は、中学入試、高校入試、大学入試の英語試験の方法やその成績に拠らない、もっと新しい方法で、英語の運用能力を捉えなおすことです。入試は学歴に関係するので、もちろん大事ですが、英語は、それらの関門ごとに区別できるような段階を踏んで上達するとは限りません。この点、私は単純に、英語上達の三段階説を提唱しています。例えば、聞いて話して読んで書ける、英単語の数が3000くらいまではまだ初級者と言ってよいでしょう。英語の運用力は、本人が知っている単語の数だけで測るわけにはいきませんが、正しく発音された語を耳で聞いてそれと認識でき、それを、それなりに正しく発音でき、また文字で書くことができ、それらを使って書かれた文章を正しく読み取れる単語数が5000ほどあれば、その人の英語力はすでに中級レベルです。そして英語上級者となると、当然、それ以上の数の語が自在に使えます。ほんとうに上級に達しているかどうかは、英語を実際の場面で話すときのスピードや自然さ、普通の英語読本(リーダー)の英文を正確に理解しながら読むスピードも関係してきます。英語を話し、また書く際に発揮される文法力、発音やイントネーションの正しさ、英語らしい自然さ、さらには様々な構文の、時と場所がらを心得た、自在な活用、なども関係します。それらの諸要素を、英語力判定のプロの検査官が、同時的に把握・勘案して得られる総合的な評価、すなわち総合値で、英語の熟達度は測定されるべきです。
お分かりのように、さまざまな場面で英語を使いこなす力、すなわち、英語運用における総合的な練度が、当該英語学習者の現時点における英語の習熟度、すなわち英語力なのです。したがって、英語力の真に正確な測定は、一般に考えられているよりもずっと難しく、例えば、会議などで議論をリードする能力など、現実に英語を使用せざるを得ない場面を用意するなどして、多角的かつ複雑な手法や手段を用いて、時間をかけ、周到に測る必要があるのです。
ただ、理論値としての英語初級グループと英語中級(もしくは英語上級)グループの間に存在する平均学力差は、外形的かつ断定的に言えば、中学1年と大学3年(もしくは大学院生)の学力差に匹敵します。勿論、初級の学習者でもすでに中級に近づいている人もいれば、中級の学習者でもすでに上級に近づいている人もいます。しかかしそれは全体の中では比較的少数を占めるだけであり、適正なテスト結果に基づいていくつかのグループに分けられた英語学習者の、グループ別の平均到達レベルから導き出される、グループ間の目覚ましい学力差の存在は疑う余地がありません。例えば、今申し上げたように、事前のテストで振り分けられた英語初級者と英語中級者の数が、互いに均等に混じり合うクラスを、仮に人為的に作った場合を想定するなら、今申し上げた平均学力差の意味がはっきりします。つまり、そのようにして作られた混成クラスでは、インストラクターが英語初級者のグループに的を絞って授業をすれば、そのグループ属する学習者たちには、当然、一定の成果が上がりますが、クラスの残りの半分を占める英語中級者たちにとっては、その内容はすでにそのほとんどが学習済みであり、授業の大部分は復習として以外は、何の学びにもなりません。一方、インストラクターが、クラスの半数を占める英語中級者のグループに的を絞って授業をすれば、英語中級者たちはみな一定の成果を得るでしょうが、残りの半数を占める英語初級者は、英語の基礎がまだ固まっていないため、それを土台にしてのみ可能になる、より高次の学びは全く身につかず、説明の多くはほとんど理解できないでしょう。このように、教育の原理に反する授業を行えば、十中八九、惨憺たる結果が待っているのです。
C. えっ?学力差のある受講者を同一授業で教えるって?
この「要望」の真の恐ろしさは、インストラクターがその「要望」に沿うべくどれだけ努力しても、実を結ぶことはあり得ない、という点にあります。「要望」通りの成果の達成の難しさを比喩的に示すなら次のようになります。
《マイナーリーグから今年やっとメジャーリーグ入りを果たした一人の若いルーキーがいます。彼は開幕試合に出場を果たし、今バッターボックスに立ったところです。このルーキーを相手に球を投げるのは、身長190センチ、剛腕で、メジャー屈指のベテラン投手です。彼は、他チームから「魔球」と恐れられる落差の激しいカーブを中心に、切れのいいスプリット、フォーク、スライダー、ストレートと、数種類の威力のある球をもっています。マイナーリーグでの経験しか持たないルーキーが、このベテラン投手を相手にクリーンヒットを打つ確率は何%でしょうか。》
今回寄せられた要望は、この野球の比喩で言えば、プロのベテラン投手が投げ込んできた豪速球に相当します。しかもそれは、強打者でもなかなか芯に当てては打てない「魔球」です。弊社を代表する私が、今回の「要望」、すなわち、時速160キロを超える高速で投げ込まれた「魔球」に勝負を挑んだとしましょう。そのとき、おそらくは1000分の1秒以下しかないわずかな打球チャンスに対して、私の腕と肩が間髪を入れず反応し、次に全身をしならせながら渾身の力でバットを振りぬく瞬間を想像してみて下さい。「要望」という名の剛速球を、目にもとまらぬ速さで投げ込まれたとき、私はどう反応したのでしょうか。そのとき、私の心は瞬間に沸騰し、疑念と不信が一挙に爆発し、あらぬ方向に弾き飛ばされ、虚空を舞ったかと思うと、何と、次の瞬間、まるで何事もなかったかのように、たった今回復したばかりの平常心の中に柔らかく無傷で受け止められていました。そして私を受け止めたのは「問い合わせ」の電話の向こうの力強い、ゆるぎなく落ち着いた声でした。その声には芯が一本通っており、よどみがなく、100%のコミットメント(commitment=責任感、もしくは使命感)が感じられました。現代のネット社会に見られがちな用心深い計算、冷やかし、揶揄、といった要素は皆無でした。
D. 一人一コマ40分、1000円の授業
それで思い出すのは、これとは対照的な、およそ3年前のある出来事です。
そのころ、オンラインの英語講座を始めたばかりの頃の弊社は、一人一コマ40分1,000円という破格の低料金を前面に出していました。それというのも、一クラス当たり8~30人の集団授業を、毎学期、10~20コースほど走らせれば、オンライン教室として面目が立ち、経営も十分に成り立つと踏んでいたからです。市場調査もせず、そうなってほしいという無邪気な願望に凭れ掛かっていたのです。すると案の定、待てど暮らせど結果は出ず、1年余りで、用意していた資金も粗方使い果たし、当初は風船玉のようにパンパンに膨らんでいた思い上がりも、今では意気消沈して、すっかりしぼみ、独りよがりの理想は決して実を結ばないという鉄則を思い知らされた頃には、辺りは急速に視界不良となり、心は閉塞感に襲われ、かくなるうえは、例え一人と言えども受講希望者が現れたなら、採算を度外視してでも、同じ低料金で引き受けるほかはあるまいと、貧すれば鈍するの道理で、自暴自棄すれすれの、世にもひねくれた覚悟を固め、雨雲そのままの晴れやらぬ気分の中に、敢えて自らを閉ざしていました。
すると、ちょうどそのタイミングを見計らったかのように、一人の社会人男性から電話がかかってきました。お宅は一人一回40分1,000円(+消費税)だそうだが、それは非常に安い。自分の英語力は中級くらいなので、そのレベルの授業をうけたい、とのことでした。英語中級の担当者は私だったので、「非常に安い」と言われたことにはさすがにムッとしましたが、商売第一と割り切り、当面の採算は考えず、一人一コマ40分1,000円(+消費税)の線を維持したまま、即決でその社会人の受講を承諾しました。
ところがその方は、どこまで英語を学ぶことに意味、もしくは意義を見出しているのか、外からはうかがい知れないところがありました。というのも、メールを通じて受講を申し込むとき、何と偽名で応募してきました。第二に、授業(スクーリング)が始まっても、対面が前提のはずのzoom の授業に、顔を隠したまま出席し続けました。これらのことから、その方は、自分の個人情報の洩れることを異常なほど警戒していることがよく分かりました。第三に、事前に渡しておいたテキストはほとんど予習せず、余裕しゃくしゃく、お手並み拝見という感じの受講を続けました。
ちなみにそのテキストはオバマ大統領が広島を訪問した際に行った演説でした。内容は、原爆投下を含む戦争の悲劇一般を、人類史という長期のスパンの中で繰り返されてきた国家的暴力という観点から、そのより巧妙になってゆく、また科学を応用した近代戦争の本質にせまり、それを避け、平和を探求することの必要、そこに至る道筋の模索、希望の在りかを簡潔にまとめた名演説だったと記憶しています。その英語の難易度のレベルは、弊社の基準では、英語中級、もしくは中級と上級との中間くらいです。一パラグラフづつ音読してもらい、数行づつ英文を和訳してもらい、発音の間違い、意味の取り方の間違いなどを正しながら、必要な補足説明を行うという類の極めて日本的な授業でした。一見、授業はごく順調に続きました。けれども、七回目が終わったところで、「もう結構です。」と言って、先方から受講中断の申し出があり、突然、授業は終わりました。一瞬、ある種の不快感と、何とも言えない解放感とが、混じり合って押し寄せてくる不思議な心境でした。授業の全体の印象は、自分の方が一方的に相手にもてあそばれていたような、良くも悪くも波風の立たない、英語で言えば lukewarm(=ぬるま湯につかったように微温的)な授業でした。しかし、気に入らない商品がポンと返品されるのにも似た、興ざめな扱いをされ、頭の先からつま先まで、完膚なきまでに愚弄されたと感じた私は、下船しても残る船酔いを抱えた旅人、あるいは故郷喪失者のような心境になりました。
E. 一人一コマ40分、5000円で実施する完全オーダーメイド授業
けれども、この愚弄は、ただの愚弄ではありませんでした。それは私にとって一種の洗礼であり、新しい人間としてこの世に生まれ変わるための儀式だったのかもしれません。今にして思えば、その社会人の方の終始一貫してふてぶてしい、人を小馬鹿にしたような態度や物腰は、そっくりそのまま、弊社のスタイルと方針の見事なほど正確な反映だったとしか思えないのです。いや、それだけではありません。個人を相手に、複数の人数のためにこそ用意された教材や教育手法を、そのまま、何の修正も補正もなく押しつけ、空疎で怠惰なマンネリ授業を提供しただけでした。聞く側にとっては新鮮味がなく、何を言いたいのか分からない授業だったに違いありません。突然の受講中断も、そのような授業に怒りをぶちまけたものと理解すれば、納得がいきます。
しかし、ありがたかったのは、この反省は弊社にとって大きな幸運につながったことです。と言うのも、コロナで日本中が移動を厳しく制限され、代わりにテレワークやオンライン授業などが国を挙げて奨励される中、「個人の学び」を確保することの重要性に気付かされたからです。手痛い挫折体験から「目からウロコ」の学びを得た弊社は、授業提供のスタンスを見直し、ある広告会社の知恵を借りつつこれまでの方針を変更しました。グループ単位の授業ではなく、個人のニーズに的を絞った「完全オーダーメイド授業」を構想し、様々なオプションを揃えたオンライン授業としてのアイディアを具体化し、詳細をホームページに上げました。また授業料も、一コマ(40分)5,000円(+消費税)としました。そして、学びを提供する側とそれを受け取る側との間で合意(=商談)が成立すれば、受講者は10回分の授業料を前納する(希望により更新可)こととしました。この大転換は、「人情に厚く、小回りの利く少数精鋭主義」に徹した弊社の強み(=弊社の asset =経営資源)に弊社自身が気付き、それを生かし切る授業の提供に乗り出した記念すべき出発点でした。
そして今回、メールで相談を寄せられた方は、この新システムを受け入れ、弊社の定めたルールや条件をすべて了解された上で、先ほど紹介したような、一見、変則的な要望を寄せられたのでした。ちなみに、話がまとまった段階で、授業料も早々と前納されました。それは、皆様もお分かりのように、受講者側からの、弊社が魂を込めて打ち出した新方針、「完全オーダーメイド授業」への、本気の挑戦状でもあったのです。(もし弊社が、受講者の期待を裏切る旧態然とした悪しき授業しかできなければ、彼ら、彼女らは、その悪しき授業を、途中でもかまわずに投げ出し、二度と戻ってくることはないでしょう。)
F. ネイティブの英語講師との交渉
さて、弊社に在籍しているネイティブの英語講師は、元来、英会話の中級および上級クラスの担当でした。そこで、この件を持ち出すと、それでは約束が違います、と強い口調で断られました。実は、その講師は、これまで沢山の日本人学生を、日本国内、またオーストラリアの大学の集中コース等で、教えられた経験があり、彼らになら、何を話しても大抵は理解してもらえるとの自信を持っておられたのです。ところが、今度の受講希望者は、英語が全くできない社会人なので、そのような人に英語の基礎を教えた経験がなく、どうしてよいかわからない、ということでした。理屈はもちろん通っています。言い分も、いちいち、もっともです。しかし、私の正直な気持ちとしては、もし英語ができないとおっしゃる社会人が、それでも本気で英語を学びたいのなら、弊社のオンライン英語講座でこそ、しっかりと学んでもらいたい、と思いました。それに、私に相談された方は、何故か、かたくななまでに、英語ネイティブの講師の授業にこだわっておられました。それがなぜなのかは、あえて尋ねませんでした。ただ、私としては、ただひたすら、まるでわがことのように熱心にお願いしました。勿論、その間、論理的な質問には論理的に答えました。例えば英語が全くできない人には教えようがない、という主張には、「〇〇さんは全く英語ができない」と言われている人でも、日本人であれば、ある程度までは英語ができる、ということを指摘しました。また、授業料をいくらに設定してあるのか、という質問にも、以前は一人一コマ40分1000円(+消費税)だったが、現在は、一人一コマ40分5000円(+消費税)であること、今回は二人なので、一人一コマ40分4000円(+消費税)に値下げし、二人分の授業料は、一コマ40分8000円(+消費税)であることを告げました。また、学習意欲の見積もりについては、今回の申し込みは冷やかしではない、申込まれた方は極めてまじめである(dead serious)、とも告げました。
G. 私も参加する英語初級者のための授業
議論が一通り終わった後、その講師はおもむろに、これは自分にとっても挑戦かもしれない、などと小声でつぶやいた後、しっかりした声で、「それでは何とかやってみます。しかし、慣れるまでは不安もあるので、念のためにあなたにも授業に参加してもらいたい」と言われました。有体に言えば、間尺に合わないanomalous な要請には、同じく、間尺をへし折った anomalous な要請で答えた、というところでしょうか。要望を呑む条件として、私の参加を要請されたのは、共同責任という名の保険だったのかもしれません。私も講師にすべての責任を押し付けて逃げる気など、さらさらありませんでした。それは信義にもとる行為であり、人間関係を根本から壊す行為です。
しかしそれよりも何よりも、せっかく話がここまで進み、学習希望者の「要望」を真正面から受け止めた完全オーダーメイドの授業が果たして約束通り実を結ぶのかどうかを、自分の目で見届けたいという思いが、どこからともなく、むくむくと湧いてきました。そしてそこに、受講希望者と講師との出会いを取り持った私の責任、併せて、火中の栗を拾うような講師の勇気ある行動へのエール、といった要素も手伝って、降って湧いたような国際遠隔授業へのオブザーバー参加の要請を、私は快く引き受けることにしました。
授業は二週間に一度のペースで今年(令和5年)の5月にスタートしました。ところが、本人も予想しなかったことですが、英語初級の方の仕事が4月を境に急に忙しくなり、直前のキャンセルや、当分は参加の見通しが立たないといったことが重なり、まだ三回しか授業が進んでいません。しかし、私としては、オブザーバーで参加させてもらっている間に、いくつか目新しい発見をしました。それが今回、オーストラリア式英語発音教育の存在理由と、それが日本の英語教育にもたらしうる可能性について考えてみたくなった理由です。
G. 英語初心者のイメージの違い
講師との話し合いの中でハッと気づいたことが一つありました。それは、ネイティブの英語講師が常識として持っている英語初心者のイメージと私たち日本人が抱く英語初心者のイメージの明白な乖離です。私たちの心に浮かぶ英語初心者と言えば、十中八九、英語学習の初歩で躓いた人、すなわち、日本の義務教育の一環として日本人の全てが学ぶ中学英語の成績が芳しくなく、その後も英語への苦手意識を引きずっている人のことです。一言で言えば、学校で英語を学び損ねた人のことですが、それは、裏を返せば、英語初心者と言っても、中学1年で学ぶ文、例えば、This is a pen. とか、How are you? とか、How do you do? が全く発音できなかったり、意味が理解できなかったりする、などと言うことは考えられない、と言うことです。彼らは関係代名詞も五文型も知っています。名詞も動詞も知っています。動詞の過去形も、現在進行形も、現在完了形すら、人によってはよく知っています。単語にしても1000~2000語くらいは十分頭に入っています。
ところが、今回私が、英語ネイティブの講師に、英語初心者への授業をお願いして断られた表向きの理由の他に、もう一つ大きな理由があり、それは、英語ネイティブの講師にとっての英語初心者は、文字通り英語ができない人だったからでした。「えっ?待ってください。初歩の英語って、一番易しい英語のことでしょう?そんな易しい英語を、なぜネイティブの英語講師(ともあろう人)が教えられないの?」と、いぶかしく思うのは日本人だけです。実際には、英語が全くできない人が本当にいた場合、その人に英語を教えるのは、英語ネイティブの講師にとっては、中級や上級の人に英語を教えるよりもはるかに難しいのです。彼らにとっての英語初心者は、英語を一言も理解できず、一語も発音できず、アルファベットの一文字も書けない人のことでした。まるで赤ん坊さながらに、英語の単語を一つも知らず、一語も聞き分けられず、また発音することもままならない人に、英語ネイティブの講師が、英語を全くの初歩から教える場面を考えて見て下さい。まず第一に、説明に使う英語自体、全く相手に通じません。次に、アルファベットを教える際にも、最初の文字 a から、順に一個一個、綴りや発音を教えなければならず、単語の読み方にしてもーーその理由はこの後すぐに詳しく説明しますがーーそれを正しく読めるように教えるには、途方もない量の資料を揃えて臨む必要があります。それが、実際には、どれほどの量か、初級英会話の授業を頼んだ私自身、ほとんど考えてもみませんでした。しかし、実際に、オブザーバーで授業に参加してみて、その負担の重さを、講師によって用意されたパワーポイントの資料の多さから、ひしひしと感じることができました。我が不明を恥じると同時に、準備の周到さに驚愕し、オーストラリア式英語発音教育の底力を見せつけられたように感じました。講師は、英語の初心者にとって、決して一筋縄ではいかない、英語発音の不規則性を、見て見ぬふりをするのではなく、真正面から受け止め、ご自身、幼少期に受けられたはずの西洋流英語教育の知見をベースに、英語発音の規則を、例外の束とセットにして、「スペリングと発音の関係」という観点から、的確かつ詳細に、説明されたのです。
H. スペリングと発音の関係を考えることの意味
「スペリングと発音の関係」だって?それ、何のこと?と思っていらっしゃる方はいらっしゃいませんか。それは次のようなことです。つい今しがた述べたように、英語ネイティブの人たちにとっての英語の初心者は、赤ん坊にも似て、アルファベットの発音の仕方を全く知らない人のことです。ですから講師は、色々な単語を例として提示しながら、それらの読み方を示し、その読み方が条件によって異なることをめぐる法則性、すなわち、同一のアルファベットの、条件次第で異なる読み方の例を、システマティックに解説されたのです。でも、「条件次第で異なる読み方」って、一体、何のことでしょう?耳慣れない言葉ですね。
英語は、日本語の五十音に相当するアルファベット26文字の読み方の全てを覚えれば、原則的には、書かれた英語は全て声に出して正しく読めるのですが、実は、そこに若干、含みがあるのです。日本語と異なって、英語は、語を構成する際のアルファベットの読み方(発音の仕方)に例外が多く、実際問題として、アルファベットの例外的発音への、多岐にわたる膨大な予備知識がなければ、ほとんどの単語は正確には読めないのです。例えば、アルファベットの c は、city やcite や pace では/s/ と発音されますが、cloud や cook や basic の場合は/k/ と発音されます。また、special では、おなじ c でも、/ʃ / と発音されます。また、日本語の「ア」「エ」「イ」「オ」「ウ」に対応する五個のアルファベット、すなわち、a, e, i, o, u は、それ自体では、決まった発音を持たず、それぞれ複数の可能性の中で存在しています。例えば、 a を取り上げるならば、make の a は/ei/ と発音されますが、mad の a は/æ/ と発音され、 small の a は/ɔ:/ と発音されます。
一般にどの言語においても、所与の単語は、それ以外の全ての単語と、互いにスペリング(=個々の単語を構成する、アルファベットの弁別的組み合わせ)が異なることで、発音・意味・文法的役割が、それぞれ他から区別され、そのことによって、各々が、所与の言語の欠くことのできない構成要素として、コミュニケーション上不可欠の機能を、他の諸々の単語それと連携しつつ、遺憾なく発揮し、そのことによって、その言語を使用する人々の日々の生活を支えています。
ところが、英語においては、先ほど挙げた五個の母音に対応する五個のアルファベットの任意の一個を内包する単語が、それと同一のアルファベットを内包する別の単語に置き換わるごとに、その同一のアルファベットは、単語を弁別するための異なる子音の組み合わせに遭遇します。するとそのとき、そのアルファベットは、それらの特定の子音の組み合わせに反応して、それまで可能性として存在していた複数の発音の中から、ある一個の発音が選ばれ、実体化する仕組みになっています。したがって、日本人の目から見れば、英語の母音の発音は、その母音を取り巻く子音の組み合わせが別の子音の組み合わせに取って代わられるごとに、言い換えれば、単語が別の単語に置き換わるごとに、くるくると猫の目のように変わるのです。日本語の五十音の場合のように、音と文字とが、アプリオリに、一対一の対応をし、独立的、かつ固定的に発音を決定するわけではありません。では、英語に潜む発音の端倪すべからざる変幻性を規律的に支配する原理はないのかと言えば、決してそうではありません。ただ、無数の断片のように存在するそれらの規則を、網羅的に一覧表としてまとめるのは、元来、至難の業です。
I. スペリングから発音を導くための変換規則:フォニックスの発明
しかし、英語圏では、昔からスペリングと発音の間の関係が詳しく追及され、ついに、それらを集大成した対応一覧である、英語発音指導システム、すなわちフォニックスが開発されました。かくして、英語ネイティブによる英語ネィティブの子供たちへの発音指導、すなわち、英語のアルファベットの正しい読み方の指導が、英語特有のスペリング特性、すなわち、英語に特有の、アルファベットの配列特性に配慮しつつ、単語別に、あるいは、単語グループ別に、教えられるようになったのです。そして、その結果、何が起こったでしょうか。英語圏では、正しい発音が、正しいスペリングを、かなりの精度で、自動的に、推測させるまでになったのです。スペリングと発音の関係を、整合的に説明する暗号が、事実上、全て解けた状態にあると言っても同じことです。英語にも同音異義語が一定量存在しますが、全体から見れば、その分量は微々たるものです。
J. 日本になぜ同音異義語が多いのか?
しかし、発音を整理して、漢音にはあった四声を受け継がなかった日本語流の漢字の読み方は、日本式発音の規則に合わせて簡易化され、平板になりました。日本人にとって、漢字は、極めて読みやすくはなりましたが、四声を無視したため、無数の同音異義語を抱えることになりました。日本語では、このため、コミュニケーションの成立を陰で支える、個人の膨大な量の経験値と言語的記憶を瞬時に検索することなしに、言い換えれば、人間の言語・情動・判断にかかわる総合的、もしくは統合的な判断を支える「文脈」を参照することなしに所与の発音を特定の文字に結び付けることは、極めて困難になったのです。例えば、「サンセイ」という音に対応する漢字を取り上げても、「賛成」「酸性」「三省」「三世」「参政」などがあって、「文脈」への参照なしでは全くお手挙げです。
さて、ここまで読んでこられた方は、それにしても、英語圏ではなぜそこまで英語発音が複雑で、マスターするのが難しいの?日本では、簡単ないくつかの英語は誰でも知っており、みんなそれらを正しく発音することができるのに?と思っていらっしゃいませんか。でも、そこには、日本人が英語を学習するにあたって、よほど注意しなければならない事柄、さらに言えば、日本人が国際的な場面で、英語を使って外国人と対等に交わることのできる、並み外れた英語力を身に付けようとするとき、死活的に重大な問題が潜んでいるのです。でも、その話に移る前に、英語の四技能に関する常識を一つおさらいしておきましょう。
K. 英語発音を学ぶことの重要性について
ご承知のように、英語の半分はスピーキングとリスニングであり、残りの半分はリーディングとライティングです。英語の運用に関するこの四つの側面を、私たちは、英語の四技能と呼んでいます。ところで、日本人にとっての英会話は、英語の四技能のうちの、前の半分を指します。しかし、一般に「英語」と言えば、最初の半分に加えて、後者の半分も含みます。そして、学習者は多くの語のスペリングを覚え、それらのスペリングを正しい発音で声に出して読むことができなければなりません。言い換えれば、単語の発音が正しく人に通じるよう、正しく発声されなくてはなりません。つまり正しい発音を学ばなければ、英語学習者は、決して英語を学んだことにはなりません。でも、教室で、先生が正しい英語の発音を日本人に教えるのは、一般に日本で考えられている以上に、難しい準備が必要なのです。この事実を事実として、しっかり把握したとき、私たちは、改めて、オーストラリア式英語発音教育の意味とその可能性というテーマが、十分考察に値するテーマとして、しっかり意識され始めます。ですから、まず、日本における英語発音教育の問題点をおさらいしておきましょう。
L. 日本における英語発音教育の問題点 英語発音の難しさ:スペリング通りには発音できない
英語発音の難しさは私たち日本人の間で、とっくに常識になっています。このテーマは、英語文法の必要性、並びに難解さと、セットになっており、特に戦後、アメリカ英語がどっと日本に入ってきて以来、日本人の脳裏に深く刻まれて今日に至っています。そこで、まず簡単に振り返っておきたいのは、ここ10年ほどの間に文部科学省が主導して全国に普及させた、小学校や中学校へのALT(Assistant Language Teacher=語学指導助手)の派遣事業です。当初、ALTに期待されていた役割は、英語の発音教育に限ったものではありませんでした。彼らには、英語で話す練習、リスニング力の強化、異文化理解の普及と増進、などが期待されてきました。ただ、英語発音を正しく学ぶことの重要性は、近年、日本人の間でますます理解が進み、今では、ALTの先生方に期待される達成目標のうち、決して小さくはない部分が、生徒たちの英語発音の抜本的改善、もっと言えば、日本人的発音の矯正です。そして、勿論、日本人の英語発音の矯正は、日本人の英語コミュニケーション能力の飛躍的向上に直結しており、このことの重要性を正しく評価し、理解できる大人たちの数も着実に増えてきています。
ところで、英語ネイティブを含む ALT の全般的な英語運用能力は、日本人のそれをはるかに超えているので、まず、申し分ありません。しかし、日本人がなぜ英語の発音を苦手とするのか、日本語を学んだことのない人には、その原因まではよく分かりません。彼らは教室で初めて生徒たちと対面したとき、日本語的発音の影響を色濃く残した「リズムのない変てこな」英語を耳にして、「これはひどい、これでは可哀そうだ、何とかしてあげたい。」と思っても、「でも、私はどこから手を付ければよいの?」ということになります。そこで、つい、「私の後について、大きな声で言ってみましょう」という、古典的な復誦方式の指導法に逃げてしまいます。勿論、これはこれでオーソドックスな良い方法ですが、日本人を相手にする場合は、もっとかゆいところに手の届く、きめ細かい指導があってしかるべきなのです。しかし、さすがの ALT にもそこまでは期待できないとなると、せっかく文部科学省に肝いりで全国の都道府県に補助金を配り、日本人の英語発音の矯正に向けて、満を持して実施したALT派遣事業も、残念ながら、大方の期待を裏切ってしまう可能性が高いのです。では、日本の公的機関から「義務教育」の一環として、少なくとも中学の3年間、「学校英語」を学ぶことを期待されている私たちは、一体どうすればよいのでしょうか。私たちの行く手を阻むこの一大障害を取り除き、この国民的隘路から私たちを救ってくれる起死回生の一手は、果たしてこの世に存在するのでしょうか。
M. しかるべき日本人から英語発音を学びなおすことの重要性
私の処方箋は、簡単明瞭です。「今さら何、それ?そんな馬鹿な!」と思われるかもしれませんが、ほかの誰からでもなく、「しかるべき日本人から、英語発音を学び直す」ことです。灯台下暗しです。勿論、確かに、英語発音を学ぶことの超が付くほどの難しさに加えて、英語発音を何とかマスターした日本人の超が付くほど少ない事実は、私の提案の実行可能性の半端でない少なさを指示しています。ただ、少数とは言っても、英語発音を完全にマスターした日本人は、皆さんもよくご承知のように、決して一人や二人ではありません。本気で探せば、必ず、何十人、何百人と見つかります。それだけではありません。日本人でありながら、見事に英語発音をマスターした人なら、日本人にとっての英語発音の難しさの原因、並びにその対処法を、母語である日本語の特徴を踏まえ、正確に割り出すことができます。そこで、ネイティブの英語発音と平均的な日本人の英語発音との差を、細部まで知りつくしたうえで、そのギャップを埋める厳しい訓練を自らに課し、結果的に、英語ネイティブの発音と比べてもそれほど遜色のないレベルにまで達した人が、もし一人でも見つかれば、私たちはその人に、全幅の信頼を置きつつ、日本人への英語発音教育を任せるのが極めて妥当ではないのかと、申し上げているのです。
そのような人なら、日本人の発音を徹底して矯正することが可能です。しかるべき英語発音訓練所を設けるなどして、制度化し、希望者にしかるべき訓練を施せば、目を瞠るような成果を上げることも夢ではありません。そこを巣立った人たちの一定数が次の世代の希望者を教えていけば、10年、20年と経つうちに、卒業者が幾何級数的に増えることで、英語上級者が日本に数多く輩出することになります。最終的に、都道府県単位で制度化していけば、留学に頼らなくとも、こと英語教育に関しては、極めて安価に、かつ効率よく成果を上げることが可能になるはずです。
N. 見過ごされてきた英語発音教育不在の日本の英語教育
でも、これまで150年もの間、ある種の既成概念に取り込まれ、ぬるま湯につかり続けて来た多くの日本人にとって、これは唐突かつ突飛な考え方でしかなく、「おとぎ話」の類としか聞こえないかもしれません。そこで、一旦頭を少し冷やすために、各々、自分に向かって静かに次の質問をしてみましょう。「それでは、私自身は、日本人の英語発音への、極度の苦手意識が、一体どうして生まれたのか、その由来と現状と解決策を、論理的に分かりやすく人に開陳することができるだろうか?」と。
もうお分かりだとおもいます。このテーマは、日本人がこれまで自らに問いかけることを意識的に避けてきた問であり、タブーとして、長いあいだ真の解決が持ち越されてきた民族的懸案なのです。この問を自身に向かって発し続ける勇気のない人は、その場で思考停止に陥り、解決を他者にゆだね、安全地帯に逃れます。これが「逃げ」でなくして何でしょう。となると、この問題は、私たち日本人にとって見かけよりもずっと重く、その解決は、さらに一層むずかしいのです。これは、これまで長いいあいだ、日本人の意識の片隅に、ひっそりと存在し続けてきたのですが、いま改めて真正面から取り上げるとき、多くの方が、「なるほど、あまり簡単な話ではなかったのですね。」と、このテーマを追求することの必然と正統性が、100年以上の年月を経て、いまやっと腑に落ち、心から納得されるはずです。
O. 巨大な文化の壁として日本人の行く手に立ちはだかる英語発音
結論的に言いますと、日本人にとって、その矯正を含めた、改善課題としての「英語発音」の問題は、日本文化の中心に位置し、その精華ともいうべき日本語、そして日本人の心そのものでもある日本文化の、ほの暗い無意識のレベルにまで達する、鋭い問いかけを含んでいるのです。その証拠に、今でも、平均的な日本人は、「英語の発音」と聞いただけで、冷静になるどころか、逆に、頭に血が上り、困惑の極みに達した後、吐き捨てるように、こう言うはずです。「いやもう、あの立て板に水の、それはそれは滑らかで、流暢この上ない、あの英語のリズムでしょう?それに、日本語とは似ても似つかない色合いを持つ、あの高速の英語発音!とくれば、私などとても無理。逆立ちしても、真似なんかできませんよ。」あるいは、「英語って、ほら、あれよ、リスニング(聞き取り)の難しさ!こ・れ・が一番の問題なんだよねー。」などと、半ばはにかみ、半ば悔しそうな、ため息にも似た一言が聞こえてきそうです。つまり、日本人は「英語をしゃべることは超が付くほど難しく、ことに、リスニングの難しさにも直結している英語の発音は、どうあがいても、合格点がもらえるレベルにまでは学びきれるものではない。」と極めて悲観的に、というよりも、絶望的に、感じているのです。この自虐性の、しかし、妙にきっぱりとした口調は、「頼むから、日本人の英語発音に対する苦手意識の由来を、底の底まで探ってくれ」とでも、呟いているように響きます。日本人がすでに直感的に感じ取っているのは、日本語と英語の間にはっきりと存在する、海のように深く、想像を絶するスケールを持った文化の溝なのです。この溝を埋めるには、少しばかり手間がかかります。が、まず必要なのは、前段階としての、正しい現状分析と評価です。
P. 日本人に英語発音の学習を難しくさせている二要因
少し冷静になって考えれば誰にでもわかることですが、日本人が英語の発音を難しいと感じる理由は、二つあります。一つは、英語のスペリングと英語の発音の間に見られる、質(たち)の悪い不整合です。そしてもう一つの理由は、日本語には無くて英語にはある発音、加えて、多くの点で日本語とは逆のベクトルを持つというほかはない、英語特有のイントネーションの存在です。この後者の理由は、英会話学校などでは重点的に教えられているので、多くの方が既によくご存じです。問題意識の共有は比較的簡単だと言えますが、後者のポイントは、日本の英語教育ではあまり強調されることはなく、問題意識の共有がほとんどなされていません。したがって、ここでの議論は、ひとまず、前者の理由に集中します。
Q. 英単語をスペリング通りに発音できなくさせた英国の歴史
英語のスペリングと英語の発音の間に見られる質の悪い不整合とは何かと言えば、日本人の英語初心者が、知らない英語の単語を見たとき、その単語のスペリングを見て予想する発音と、実際に英語母語話者によって発音される音との間には、相当に大きなずれがあるということです。それは、主として、英国が多年にわたってデーン人、ケルト人、アングロサクソン人など、多くの民族の侵入を許し、最後に、1000年近く前にノルマン人の侵攻を許し、以来数百年にわたって言語的弾圧を受けた、過去の歴史の結果であるとはいえ、今や世界中の英語学習初心者に、甚大な影響を与え、彼らに、英語文の音読(reading of English texts aloud)を著しく難しい課題に変えてしまったのです。いくつかの例を見ていただくとお分かりいただけることですが、基本英単語についての、英語学習未経験者の発音予想は、ほぼ確実に外れます。例えば、table はローマ字式に発音すれば、「ターブレ」となるはずですが、実際の発音は「テイブ(ル)」です。また、you はローマ字式に発音すれば「ヨウ」ですが、実際の発音は「ユー」であり、同様に、knife は「クニッフェ」ではなく、「ナイフ」です。他にも、 have は「ハベ」ではなく、「ハブ」であり、paper も「パペル」ではなく「ペイパー」であり、are は「アレ」ではなく、「アー」であり、orange は「オランゲ」ではなく「オリンジ」であり、 line は「リネ」ではなく、「ライン」です。また、lion は「リオン」ではなく「ライオン」であり、toは「トー」ではなく「トゥー」であり、for は「フォル」ではなく「フォー」です。
R. ローマ字の知識が暴く英語発音の不可解さ
ところで、今当たり前のように「ローマ字式」と言う言葉を使いましたが、私たち日本人は、英語を学び始める直前に、小学校でローマ字を学習します。ローマ字は、英語に使われるアルファベット26文字と同じ文字です。面白いのは、このローマ字を使って、日本人が知っている大抵の日本語を表音的に記述することが可能だということです。そして実際、学校では、自分の名前をローマ字で書く訓練を受けます。ローマ字の名前はパスポート、各種のカード、申請書、などにもよく使われます。また、鉄道の駅の名称、道路標識などにも、その正しい読み方を伝えるために使われるため、ローマ字の知識は事実上不可欠です。しかし、何という不運でしょう。このローマ字の知識が、学校で私たち日本人が英語を学ぶときには邪魔になるのです。上に見たように、ローマ字式の読み方が、英語には全く通じないというだけでなく、日本人は、ローマ字の知識があるばっかりに、英語の発音を一層、間違えやすくなるのです。例えば、home はローマ字の知識があれば、「ホメ」と発音したくなります。けれども、正しい発音はご承知のように「ホーム」です。同様に、rain は「ライン」と発音したくなります。しかし、実際の発音は「レイン」です。また、boat は「ボアト」と発音したくなりますが、実際の発音はご存じのように「ボウト」です。
このように、日常よく使われている英単語のスペリングが、ローマ字を知っている人に予測させる発音と、実際にネイティブの英語話者たちが発している音との間に、顕著な不整合が幾つも見つかるにもかかわらず、私たち日本人は、本来なら由々しき問題であるはずの、英語発音の予測不可能性を、全く問題にしません。99%以上の日本人は、多分、能天気にもほどがありますが、「英語は所詮、外国語であって、多くの単語の発音予測が、現実にどれだけ外れても、そんなことは想定の範囲内です。」と言わんばかりに、一切を、諦めてかかっています。しかし、世界の多くの言語の中において、英語を眺めるならば、英語発音の予測不能性の異様な高さは、隠れようもないほど、くっきりと浮き彫りになります。それは他の言語ではあまり目立たない現象であり、英語こそが、例外中の例外なのです。ということは、それとは真逆に、日本語の発音の驚くべき整合性、例外を許さない鉄壁のルールは、むしろ自慢してもよいくらいであり、世界の言語の常識から言えば、日本語は正に優等生であり、英語に比べてはるかに健全であり、模範的にまともなのです。日本語には、英語と同様に、無数の語が存在しますが、一語の例外もなく、平仮名、もしくは片仮名を使うことで、その読み方を、日本語式にではありますが、正確に記述することができます。日本語は、五十音順に語が配列されている国語辞典、もしくは、漢字の読み方が必ず平仮名で示されている漢和辞典を引くことで、日本語の初級学習者でさえ、どんな語、あるいは語句であっても、直ちにそれらを正しく発音することができます。平仮名(あるいは片仮名)は、任意の一語を構成する要素、すなわち、語の一部になり得ると同時に、漢字や外来語や難しい人名や地名の読み方まで、簡単明瞭に表示することができる、極めて便利な発音記号としての機能をも持っているからです。そして、実際、辞書や各種の辞典類を始め、パスポート、身分証、各種申請書、処方箋、その他、多くの場面で、人々に漢字の正しい読み方を教える、重要で便利な発音記号として使われ、私たちの生活を支えています。ところが英語には、そのような便利な符丁は存在しません。
S. ローマ字式発音に近いヨーロッパの英語以外の諸言語
このように、英語では、table を始め、多くの英語の単語において観察される、スペリングと発音との間の大幅な隔たり、もしくはずれは、日本語には全く見られないのですが、同じように、ヨーロッパの他の言語、特にラテン系の言語においても、実は、ほとんど見られません。例えば、ドイツ語で「今日は!」に相当する挨拶はご承知のように Guten tag. です。これは、ローマ字式に「グーテンターク」と発音すればよいのです。気をつけたいのは、g の発音くらいで、「グ」ではなく「ク」と発音します。また、フランス語の「今日は!」は、 Bon jour. です。ほぼローマ字式に「ボンジュール」と発音すれば十分通じます。気を付けたいのは jour の ou は「オウ」ではなく「ウ」もしくは「ウー」です。私の知る限り、フランス語の ou は、例えばoui (「ウイ」と発音し、英語の yes に相当する)のように、鋭く短く「ウ」と言うか、「ウー」と鋭くやや長めに発音されます。
では英語の「今日は!」はどうでしょうか。Guten tag. や Bon jour. に相当する英語は、 Good day. です。発音は英国式でも、米国式でも、「グッデイ」です。挨拶として日常的にこの言葉を多用するのはオーストラリア人だけですが、Good day は「良い一日を(祈ります)」という意味を、ドイツ語やフランス語と共有しているので、発音の偏りを調べるのには適しています。そこで、Good day をローマ字式に発音するとどうなるでしょうか。「ゴオードダイ」となるはずです。いかがですか。「グッデイ」とは大きく異なることがお分かりでしょう。オーストラリア人は「グダーイ」と発音しますから、英国人や米国人の「グッデイ」よりはましかもしれませんが、それでも「ゴードダイ」との隔たりは歴然としています。どうしてこんなことになるのでしょうか。
T. 英語単語に多いスペリングと発音の間の不整合
少し細かく見ていきまと、まず、day のay は「アイ」ではなく、「エイ」と発音します。他の例を挙げれば、「支払う」の pay は「ペイ」、「言う」の say は「セイ」と発音します。そんなのは当たり前じゃないか、と思われましたか。では逆に、お尋ねします。「エイ」と発音するのは ay だけでしょうか。もしそうなら、ay は「エイ」と発音する、と覚えておけば、それ以上に問題は複雑化しません。フランス語の ou は「ウ」もしくは「ウー」と発音する、と覚えておけばまずは一安心でした。ところが英語ではそうはいきません。「エイ」と発音するスペリングは他にもあるのです。例えば、aid(=「援助」)の ai も、 they (=「彼ら」)の ey も、 bob-sleigh (=ウインタースポーツの「ボブスレー」)の eigh も、「エイ」と発音します。また、cake の a も「エイ」です。いかがですか。ここまで「エイ」の発音を共有する異なるスペリングが複数個存在するとなると、スペリングと発音の間の対応原則が少なからず揺らいできます。特定の発音をめぐって、対応するスペリングの特定ができない事例が存在するのは由々しき事態です。スペリングに紐づけられているはずの英語発音には、説明のつかない気まぐれな例外が多数存在するのではないか、という疑問が残るからです。
分析をさらに進めましょう。good の oo は、ご承知のように、短めに緩く「ウ」と発音しますが、 spoon の oo は鋭く長めに「ウー」と発音します。 moon もしっかり長めに「ムーン」と発音しますし、 cool も同様に「クール」です。ところが、日本人はコックと呼んでいる「料理人」を意味する cook は「クック」と発音します。cook の oo は短めに緩く「ウ」と発音することが分かります。また、「見る」の意味を持つ lookも「ルック」であり、「足」の foot も「フット」です。しかし、「食べ物」の food は「フード」です。「フッド」ではありません。一方、「頭巾」の hood は、日本語ではフードと言いますが、英語での正しい発音は「フッド」です。下手な未来予測に似ていませんか。それとも、丁半のサイコロ賭博に似ていますか。
このように、英語の発音は、キツネとタヌキの化かし合いに似て、摩訶不思議であり、一見したところ、どこまで行っても正体が見えないのが現実です。このような英語に付き合わされる日本人としては、さすがにもう、憮然たる思いになります。でも、ひょっとしたら、例外の多い英文法に似て、全体的にはそれなりに筋が通っている、ということかもしれません。そこで、念のために、もう少し視野を広げるために、全く別の語に当たってみましょう。
例えば、「豆」を意味する pea 、「平和」を意味する peace に共通の要素である ea は、ご承知のように、鋭く長めに「イー」と発音しますが、それでは ea はいつでも「イー」と発音するのでしょうか。もしそうなら、話は簡単です。ところが、「頭」を意味する head 、「牧場」を意味するmeadow 、「物差し」を意味する measure 、「皮」を意味する leather などに共通する ea は、短く緩めに、「エ」と発音します。一方、「離れる」という意味の leave や 「指導者」を意味する leader 、「葉っぱ」を意味するleaf、また「読む」を意味する read に共通に含まれる ea は、「イー」と、鋭く長く発音します。また、leap は「跳ぶ」という意味の自動詞で、発音は鋭く長い「イー」を含む「リープ」ですが、その過去形と過去分詞は、いずれも leapt (米語ではleaped が一般的。発音は「リィープト」もしくは「レプト」。)で、発音は「レプト」です。 ここでは ea は、明らかに、短く緩く「エ」と発音します。また、「読む」という意味の動詞 read の現在形は read で、発音は「リード」ですから、そこに含まれる ea は鋭く長い「イー」ですが、その過去形と過去分詞は、形こそ同じread ですが、発音は、短く緩い「エ」を含む「レッド」です。いかがですか。ここでもまた、学習者をあざ笑うような、説明しがたい不規則性が露呈しています。
では、私たちは、これまで多くの実例を見てきた、複雑骨折を思わせる英語のスペリングとその発音の間の謎に包まれた一連の不整合を、一挙に、総体として説明してくれる何らかの複雑精妙な計算式ーーもしそれがあるとしてーーを見つけることができるのでしょうか。
U. 発音教育を完全に放棄してきた日本式英語教育
しかし、その前に、日本の教育の現場で、この問題に関して取られてきた「現実的」な対応策をおさらいしておきましょう。日本の中学・高校における戦後の英語教育では、日常よく使われる1000~1500くらいの単語を第一段階として、次に3000~5000くらいの単語を第二段階として、そのスペリングと発音と意味をひたすら丸暗記させ、高校入試、大学入試の厳しい関門を潜り抜けさせようとしてきました。これは、エリートたち、親の期待を一身に背負う全国の受験秀才には、ひょっとしたら、なんら問題のない方法かもしれません。彼らは学校や塾の教師に、入試を突破するまでのわずか数年の辛抱だからと、呪文のように言い聞かせられ、ひたすら、膨大な数の単語の意味と発音を暗記します。しかし、平均的な日本人の場合はどうなるのでしょうか。例えば、海外で売られているベストセラーの一冊をたまたま買って読んでいたとしましょう。教科書で習ったことのない、見知らぬ単語が次々に出てきたら、彼らはどうするでしょう。スペリング通りに発音すると危ないかも、と思いつつ、とりあえず何らかの発音をするかもしれません。何しろ、発音の伴わない語は存在しないのですから。でも、もうお分かりのように、当てずっぽうで英単語を正しく発音できる確率は極めて低いのです。見知らぬ単語を、我流発音で覚える悪い癖がついた人の人生は、譬えが悪すぎるかもしれませんが、まるで車の無免許運転者並みに悲惨なものになるでしょう。これが国民の大多数に及ぶとなると、想像するだに恐ろしく、断じて許容しがたい事態です。日本の英語教育に、このような盲点があることを天下に晒すことになりかねません。単語を覚えれば覚えるほど、その人の英語が海外で幾何級数的に通じにくくなるとしたら、背筋が凍る悪夢です。そもそも、これがすでに現実でないと、誰が言いきれるでしょう。
V. 発音記号を教えることによる英語発音教育の実践について
では、この悪夢を遠ざけるにはどうすればよいのでしょうか。私たちに必要なのは、前途有為の若者が、英語の発音に正面から取り組み、堂々と正攻法でマスターする方法です。私の知る限り、無数の地雷の仕掛けられた戦場にも似た、英語発音の無法地帯を、無傷で、安全に、走り抜ける方法が、たった一つあります。それは、発音記号を用い、合理的、実践的に、英語の発音を教える方法です。これは、私が、自分の責任において、普通、日本の学校では絶対そうしないことを承知しながら、これまで敢えて採用してきた教育手段です。学生諸君は、ほぼ例外なく、学校現場で携行が求められる英和辞典には、必ず発音記号が使われていること、そして、それぞれの発音記号に対応する発音を正しい方法で個別にきちんと習得しさえすれば、どんな英単語語でも正確に発音できることをすでに知っています。私はこの事実に目を付けたのです。では、私は一体どんなふうに教えたのでしょうか。実際の授業風景を分かりやすく端折って再現してみましょう。
私は、具体的な単語を例に出して、自分で発音してみせ、その発音を各自、自分の耳で聞いてもらいます。悪びれることもなく、自信をもって自分の発音を聞かせる教師は、学校にも自分の周囲にも、一人もいないので、彼らは最初、あっけにとられ、びっくりしますが、同時に、興味津々で聞いています。やがて、彼らの短い「試し聞き」の時間が経過すると、私の発音が、意外にも、正確であるとの認識が、天から授かった自分の聴覚を通じて、心の奥深くまで、浸透していきます。次に私は、その単語に含まれる難しい発音を個別に取り出し、それに対応する発音記号を板書します。その記号が表す音の特色を続いて説明し、その音を出す方法を具体的に教えます。次いで、銘々、自分でその音を出してもらいます。その後、私は、各自、できるだけ多くの時間を割いて、帰宅後も、英語の発音の練習に励むことを勧めます。
彼らは総じて熱心に学びました。破裂音の実演を交えた練習では、クラス全体が爆笑して笑い転げる場面がありました。クラスの全体が爆笑したのは、何だそんな風にすれば正しい/p/の音が出せるのか、という新しい発見の意外さと、自分にもその音が出せるかもしれない、いや出せそうだ、という健全な期待感と、抑えようもなく内部に膨れ上がる強烈な意欲が、一度に各自を襲ったときの自然な反応なのです。そしてこれこそが、起死回生の奇跡なのです。では、なぜ、これだけのことが一瞬で起こったのかと言えば、彼らが、真剣に、虚心坦懐に、正しい発音を、正しく聞き、それが正しい発音だと確信した瞬間、今度は、自分が正しく発音し、それを徹底反復すれば、やがて必ず、自分も、正しい発音ができる、ということを、100%ポジティブに受け止め、各自の身体的直感が、理屈を超えて、正しく理解したからです。
でも、発音練習の実際の効果が一人一人の「心身」に「命」となって定着するまでには、一定の時間がかかります。長い練習期間が必要なのです。長期にわたるフォロー・スルーを組み込んだ授業システムが別途必要なのです。英語リーディングは、単に英語を黙読するだけでなく、音読を前提としています。実際には、徹底したリーディング(=音読)指導が求められるのです。
W. 日本語にない英語の発音をどうするか?
ところで、英語発音の難しさは、スペリング通りに発音しても必ずしも正しい発音にはならない、ということに留まりません。すでに述べたように、もう一つ大きな問題があります。それは、英語には日本語にない音がいくつも存在する、ということです。これは日本人にとって、そんな馬鹿な、と開いた口が塞がらないような、克服不可能としか思えないほどの深刻な問題です。発音の学びに苦労したことのある多くの方が、すでにご存じのように、例えば、l とr 、 s とsh と th、b とv 、f とh などの子音の区別は、日本語には元々微塵も存在しません。これは、英語学習の観点から見るとき、一体、何を意味するのでしょうか。これは、それらの音が、ネイティブの人たちと同じようにきれいに区別して発音できるようになるまで、英語の発音の仕方を、一から徹底的に学び、口がだるくなるまで、毎日何時間も、繰り返し練習しない限り、決して正しく発音することはできない、ということを意味しています。一方、教える側に立てば、これらの区別を一通り初心者に教えるだけでも、実は何日もかかります。また、教え方の一例とし ては、right -light, sign- shine, sick-thick, see-she, berry--very, find-hind などをペアーで発音する練習などがあります。学習者はこれらを区別して発音することができるようにならなければなりません。また聞いて差異が分かるようになる必要もあります。そのためには、基本的な口慣らしと耳慣らしを、毎日一定時間、ノルマとして、厳しく行わなければなりません。
X. アルファベット a の発音の四変化を誘発する取り巻き子音の存在
ところで、英語の発音の難しさは、子音の発音の難しさに留まりません。母音にも及ぶからです。そもそも、英語のほとんどの単語は、26個あるアルファベットのうちの、1個から十数個の異なる組み合わせで出来ているのですが、例えばアルファベットの a で表される母音の場合、この母音を前後に取り巻く異なるアルファベットの組み合わせによって、 a の音が何通りにも変化します。日本人の場合、母音は「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」の五つと決まっているので、「ア」が四通りに変化すると聞かされると、唖然とし、眩暈を感じます。例えば、中央に a を持つ四つの語 cat, cake, call, car を見て下さい。この四語においては、発音されたときの a の音は、お互いに他と全く異なります。
しかし、それを確かめる前に、これらの四語に共通する音韻構造を確認しておきましょう。これらの四語はいずれも「子音+母音+子音」という構造を持っています。次に相違点がどこにあるかを見てみましょう。相違点は四語を区別する要素として、異なる子音が使われているということです。上記の四つの語の場合、それぞれ、互いに異なるアルファベットが、母音 a の前後を取り囲むことで、四つの異なる語が形成されていますが、互いに異なるそれらのアルファベットの組み合わせは、 a をあんこのように中央に挟みながら、四つの異なる単語を構成する、弁別的子音群を提供していることが見て取れます。このように、互いに異なる子音が同一の母音をはさんで、四つの単語の弁別要素として働くのは、地球上の全ての言語のメカニズムにとって、おそらく当然のことです。しかし、英語の場合、特殊と言えるのは、同一の母音を表すはずのアルファベット a の発音が、この四語間で、なぜか四通りに異なるということです。この四語をカタカナで表記すると、「キャット」、「ケイク」、「コール」、「カー」となります。母音の a に対応する発音だけを抜き出すと、「ヤッ」、「エイ」、「オー」、「アー」と四通りになることが確認されます。ここから分かることは、英語のアルファベット a の音は、前後の子音の組み合わせが機縁となって、自らも四通りの異なる発音に変化する、ということです。したがって、英語を学ぶものが、予知的に、これらをすべて正しく発音できるためには、子音の特定の組み合わせと、母音 a の特定の発音との間に存在する、四通りの関係方程式を、予め知っておかなければならないということになります。
Y. オーストラリア式英語発音教育
実は英語圏では、小学1年生に文字の読み方を教える際、単語のスペリングとそれに対応する発音を、歴史的経緯を組み込んだある種の方程式を使って、原理的かつ組織的に、教える教育手法が採用されています。英語ではそれを phonics と言います。一方、発音一般を専門に研究する学問は別個に存在し、それには「音声学( phonetics )」という名称がついています。ところで、 phonics は日本ではフォニックスと片仮名で表記され、これが一般的呼称となっています。正式な日本語訳は、私の知る限り、まだ存在していません。日本の代表的な英和大辞典を見ると、phonics は「初歩的な英語の綴り字と発音との関係を教える教科」(研究社の「新英和大辞典第五版」より)と説明されています。
では、英語圏でなぜフォニックスが教科になっているかというと、前節でも見たように、英語ではスペリングと発音の関係が一定ではなく、一見、不規則そのものに見えるからです。すでに検証した事例の他にも、例えば、book は「ブック」と発音しなければなりません。「ボーク」ではありません。また、 time は「ティメ」ではなく「タイム」と発音することは誰でも知っています。同じく、school は「スチョール」と発音していては全く通じません。英語圏の小学生たちが新聞やエッセイを読んで見慣れない単語に出会ったとき、もしスペリング通りにしか発音できなければ、英語の読み書きができなくなることは目に見えており、これは一大事です。そこで、英国の過去の歴史において、どんな予期せぬ不幸な事態が発生し、その結果、英語ががいかなる言語的損傷を被ったにせよ、結果として、スペリングと発音の関係が複雑にゆがんだことを、不幸な特殊事例として認め、その上で、多くの不規則性の集合の中に潜む、隠れた驚きの規則性をあぶりだすことに成功しました。教師や研究者が大いに努力をした結果です。こうして、英語の特異なスペリングと、特異な発音との間の、十分密接な、しかし秘密の、関係を暴き、それを法則化することで、彼らは、英語独特のスペリング特性から正しい発音を導き出すことのできる、実践的な英語発音教育法を編み出したのです。
Z. フォニックスを取り入れた日本の英語発音教育の可能性
私はこれまで、フォニックスの存在をある程度知っていましたが、それを詳しく調べたり学んだりしたことはありませんでした。ただ、自分流にではありますが、発音記号に頼る発音学習の無味乾燥から逃れるため、密かにスペリングから発音を予測する、一種のゲームを楽しんでいました。それは次のようなことをするゲームです。自分の知らない単語に出会うたびに、その単語の発音を辞書で確かめる前に、その単語のスペリングのちょっとした特徴から、その発音を推測するのです。最初の一年目は、正答率は極めて低かったのですが、二年、三年と、同じことを繰り返し、ゲームにある程度慣れてくると、このアルファベットの組み合わせだと、発音はきっとこうなるはず、という法則の存在が見えてくるようになりました。例えば、night, light, right, sight, fight はいずれも、子音+ 母音+ght 、という基音構造を持ち、終わりに、ight という共通のスペリング集合を持っています。ight の発音は「アイト」です。これらにおいて、gh は発音しませんが、この子音集合が現れると、i の発音は「イ」ではなく、「アイ」となることが暗黙の規則として働いていることが分かります。例えば、sigh は t を欠いていますが、発音は「サイ」です。つまり、 i は「アイ」と発音するのです。同様に、high も「ハイ」と発音します。したがって、 i はここでも「アイ」と発音します。i は勿論、fit, kid, pink, window, listen, hip などでは、すべて「イ」と発音します。ですから、どのようなスペリング環境のときに i が「アイ」と発音されるかは、そこに法則性が見出され鵜限り、フォニックスの研究テーマになるのです。
例えば、line, fine, dine, mine, nine, pine という一連の語群を見て下さい。ここでは、i は「アイ」と発音されます。そして、ine というスペリング集合は「アイン」と発音されます。注目すべきは、子音+母音+子音+e という基音構造です。ちょうどgh が発音はされなくとも、直前の i の発音に影響を与えたように、語の最後に e が存在することによって、それ自体は発音されませんが、これらの語の最後の子音の一つ前の母音、 i に影響を与え、これを「イ」ではなく「アイ」と発音させる因子として働くのです。実はこれと同じ原理がもう一つの母音 a をi の代わりに持つ次の語群においても働いていることが分かります。それらは、hate, late, mate, fate, gate です。ここでも、発音されない e の存在が、直前の母音 a の発音を「ア」から「エイ」に変えます。すなわち、ate の発音を「アット」でも「アテ」でもなく、「エイト」に変えるのです。でも、実際には e が最後の子音の後ろについている場合、前の母音の発音を変えるという規則はもっと広く適用されています。i が「アイ」と発音される例を幅広く収集してみましょう。例えば、knife, life, nice, rice, price, westernize, recognize, ripe, pipe, rise, size, site, cite, fire, quite, spite などがすぐ思い浮かびます。
英語には不思議な子音集合が多く存在しますが、それらはしばしば発音にも見えない影響を与えています。例えば、ll という子音集合を見てみましょう。ball, hall, tall, fall, gall, call, mall はいずれも a+ll というスペリング集合を特色としています。そしてこのスペリング集合の発音は「オール」です。他にも、a+lk で talk、a+ld で bald という子音集合の場合、それぞれ、発音は「オーク」と「オールド」であり、a はいずれの場合も、「ア」ではなく、「オー」であることを特色としています。他にも、注意しなければならない子音集合としては、kn, qu, ph があります。kn は/n/ と発音します。例としては、knife, know, knaw, knot などがあります。qu は/kw/ と発音します。例としては、question, queen, quite, quiet, quest, quote などがあります。また、ph は/f/ と発音します。例としては、photogragh, telephone, phonetic, phonogragh, iphone, philosophy, physical, physics などがあります。これらの子音集合は、それ自体が発音記号だと思って覚えればよいのです。なぜなら、これらの子音集合には、それぞれ一個の読み方しか存在しないからです。平仮名を覚えるような調子で覚えるとよいのです。
このように、「これこれの場合には…と発音する」という一対一の対応ルールを見つけ、それらを組織化して教程化したものがフォニックスなのです。
冒頭で述べましたように、たまたま、弊社の提供する授業の中に、オーストラリア人講師による英会話コースがあり、ネイティブの講師から初級の英語を学びたいという受講要望があったので、その講師を紹介したところ、初級の会話を練習する前に、単語の読み方を学ぶ必要があるだろうということで、オーストラリア式の発音教育がその受講者に実施されるのを、たまたま参観させていただく機会がありました。大変参考になったので、ここで紹介しておきたいと思い、このブログを書き始めました。日本における英語発音教育は事実上何もなされていない、という認識のもと、私の考える方法をご紹介しましたが、もう一つの可能性としてのフォニックスの考え方の概要は、以上の説明でお分かりいただけたことと思います。今まで発音に興味を持たなかったけれど、このブログを読んで一から学びなおしてみたい、と思われた方は「お問い合わせ」からご連絡ください。すぐれたネイティブの講師から英語の発音をもう一度学びなおす良い機会です。