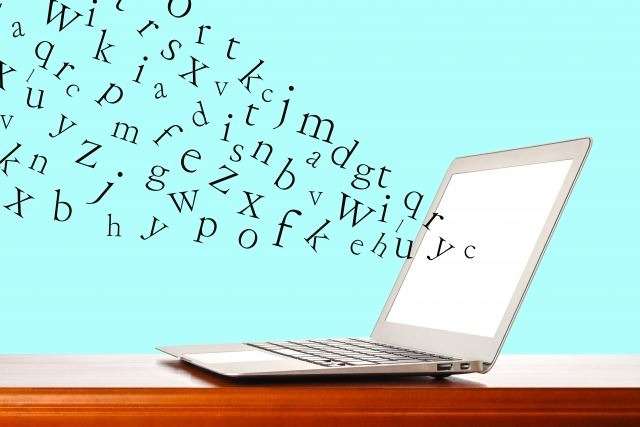英語母音攻略法:五つの「ア」音について
2022/04/28
英語母音:五つの「ア」音
発音効率って何?
1.日本人はなぜ英語に躓くのか
私たち日本人は、手もなく、話し言葉としての英語に躓きます。なぜでしょうか。その原因の一つは、日本人から見て、英語の母音と日本語の母音のあいだに、在るべきはずの音の整合性がほとんど見当たらないからです。もっと正確に言えば、日本人は、後で述べる理由によって、英語の母音体系と日本語の母音体系の間に横たわる、目で見ても耳で聞いても捉えられない、巨大なギャップを見過ごしてしまうからです。例えば、前のブログで書いたように、英語には二種類の「イ」音があるとか、二種類の「ウ」音があるという事実に、特別な訓練を受けた人以外、日本人は誰も気づかず、従って、学習の対象にもなりません。そして、今日取り上げる英語の「ア」音も、一般の日本人はまるで気にも留めません。しかし、実際には、英語の「ア」音は、例えば l とr 、sh と th など、その区別を聞き分け、また言い分けることが、普通の日本人にとって途方もなく難しいことを、すでに多くの日本人が知っている幾つかの英語子音と同様に、日本語と英語の発音の差が、極めて顕著に、かつ致命的に、表出する領域の一つなのです。
例えば、つい先日、NHKのある番組で、同時通訳者の道を歩もうとしているある若い女性が、英語の /æ/ と言う発音を、「ア」と「エ」の中間の音として捉え、その音を出すのに必要な口の開け方を、来る日も来る日も猛特訓し、ある日、ついにそれが自然に口から出るようになったと語っていました。そしてその結果、英語が飛躍的に進歩したそうです。それもそのはず、実際のところ、この音が正確に出ないと、back もcat も hat も match も、そしてThank you. さえも、正確には発音できません。このお話は多くの方に、日本人でもここまでやれるということを示した数少ない成功事例として、お手本となったはずです。私としても、地道な努力が実り、本当に良かったと思います。
でも、英語の発音の問題は、それで万事OKとはなりません。なぜなら、/æ/の音は、英語発音全体から見れば、氷山の一角に過ぎません。英語発音の全体は、多くの複雑に絡み合う要素から成っているのです。例えば、子音、母音、二重母音、長母音、強勢アクセント、曖昧母音、リズム、抑揚、などが一体となって英語発音の全体をカバーしているのです。そして、これらがきちんと連携した形で、自然体となってシームレスに身に付くまで、きちんと若い人たちに教える公的な教育機関が日本に一つも無いことが、多くの日本人の、英語によるコミュニケーション能力の伸展を阻む、一大要因となっています。同時通訳を目指すこの方が、特に /æ/ 音の訓練を始められた理由、もしくは契機が何であったのか、詳しいことは聞き漏らしましたが、恐らく、あるとき、英語「ア」音を構成する代表格メンバーである /æ/ の発音の難しさ、並びにその音の軽視すべからざる重要性に気づいたのです。そこで、自らに猛特訓を課し、顎が疲れてだるくなるのを幾度も我慢し、長く厳しい訓練の日々に耐え抜いたある日、ついにその音を「習得」されたのです。
英語発音について、多くの方は、海外生活を始めたとき、初めて問題の深刻さに気付きます。英語が思うようには通じないからです。私の知っている方で、アメリカに留学中に、「マクドナルド」の発音が誰にも通じなかった苦い経験を持っている方がいらっしゃいます。日本語的な発音を脱することがどうしても出来なかったのです。そこで、その方は、正しい発音の仕方を、アメリカの友人から、手取り足取り、基礎の基礎から、徹底的に指導してもらって、やっと通じるレベルにこぎつけたそうです。たった一つの単語でも、正しく発音出来るのと、出来ないのとでは、人生を分けるほどの、大きな差が出ることもあるのです。
本来なら、日本の政府は、こういった問題を重く受け止め、しかるべき予算を組んで、何らかの抜本的な対応を考えるべきだったのです。しかし、いまだに十分と思われる対策は打たれていません。これまでのところ、日本人の英語音声教育への全般的な関心の低さ、また、英会話への謂れなき偏見とコンプレックスによって、英語コミュニケーションの要諦である英語音声教育の重要性の認識、並びにその難しさの本質を極めようとする努力が、全くもって不十分であったために、この問題は、一見画期的に見える二つの施策、すなわち全国の小学校に英語を科目として導入し、ALT(Assistant Language Teacher)を全国の小・中学校に配置するという、私に言わせれば、問題回避型の介入を行った以外、特にこれといった手も打たずに放置されてきました。誠に残念ですが、一方で、日英両言語間に横たわる途方もなく深い言語の落差を鑑みれば、あるところまでは致し方なかったと言えます。
ただ、このままでは、日本人にとっての、英語をめぐる厳しい現実は少しも改善されません。そこで、今日は、前回と前々回のブログの続きで、英語発音の一番の難所と言ってもよい、英語母音の五種類の「ア」音について解説をしたいと思います。ただ、残念ながら今日の日本において、誰かが、自分の身の回りにいる人たちに、いきなり、英語の「ア」音は五種類あるのですよ、しっかり区別しましょうね、などと「不注意な」注意をしようものなら、たいていの人は目を丸くし、「何をふざけたことを言っているの?」と、逆切れし、却って注意した人を嘲笑し、馬鹿呼ばわりしかねません。でも、私としては、この問題への基本的な考え方と対処法を、正面から語り続けるほかはありません。
と、ここまで読まれた方の中には、「おや、そこまで言うなら、その五種類の「ア」音とやらを区別する方法を教えてもらいたいね。いや、それらの存在をまずは証明してもらおうか」と、語気鋭く詰め寄られる方々が、只今現在も、何人かいらっしゃるかもしれません。まず、後者については次のようにお答えいたします。英語の五種類の「ア」音は、五つの単語、すなわち、bad(/æ/), bud(/ʌ/), bird(/ə:/), bard(/ɑ:/) 、およびbite(/ai/)を、発音記号の使われている学習用の英和辞典で調べていただければ、いずれも「ア」音と思われる母音に対して、異なる五種類の記号が充てられていることが分かります。そこで、これらの記号が、同一の音(「ア」音)に対して使われていることは考えにくいことから、英語には五種類の「ア」音があるのかもしれない、と推理するのが自然です。ただし、これらの母音のうち、日本語の「ア」に最も近い/a/ の音は、単独では存在しません。それは、 my (/mai/)やhigh (/hai/)に見られる、/ai/ とか、out (/aut/) や loud (/laud/)に見られる、 /au/ などの、二重母音の中でしか、出会うことができません。
2.日本語母音の特色
そこで、次に、英語母音の中でも一番難しい五種類の「ア」音の詳しい解説に移りたいのですが、その前提となる知識を確認するために、学習の対象である英語の対照言語としての日本語の母音について、基本事項をおさらいしておきます。
日本語の母音(片仮名では「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」)は、音と文字の両面で、日本語教育の基軸をなしています。ですから、日本人にとって、これらの母音の発音が難しかったり、聞き取りにくかったりするはずもありません。それだけではなく、これらの基本母音の頭に /k/ という子音がくっつくと「カ」行ができ、それらは平仮名なら「か」「き」「く」「け」「こ」、片仮名なら「カ」「キ」「ク」「ケ」「コ」と表記することができます。同じ要領で、これらの基本母音に/s/ 、/t/、/n/、/h/、/m/、/j/、/r/、/w/という子音をそれぞれくっつけていけば、「サ行」、「タ行、「ナ行」、「ハ行」、「マ行」、「ヤ行」、「ラ行」、「ワ行」が出来上がります。また、濁音や半濁音を作るには、これらの基本母音に、/b/、/g/、/z/、/p/ という子音をくっつければ、付録としての「バ行」、「ガ行」、「ザ行」、「パ行」が出来上がります。つまり日本語を構成する基本の音とそれらに対応する表音文字をまとめた五十音図は、日本語の五個の母音を縦軸にとり、上に挙げた13個の子音を横軸にとって同一平面で交差させて得られたことが判明します。
他方、日本語の仮名は、私たちが小学校で学んだローマ字との相性も抜群です。「ア」=a、「イ」=i、「ウ」=u 、「エ」=e、「オ」=o というように、日本語の五つの母音と五つのローマ字(=アルファベット)が、これ以上は望めないほどぴったり対応しています。ですから、ローマ字を学んでから英語を学び始めた日本人の小学生、もしくは中学生、の多くが、英語のアルファベットに親近感を覚え、ついでにアルファベットの最初の文字 a は、英語でも必ずや「ア」と発音するに違いない、と期待に胸を膨らませ、いわば「理論値」として、a=「ア」と言う公式の存在を、自信をもって推測、もしくは想定しても、少しも不思議ではありません。
3.英語「ア」音の世にも不思議な無秩序
ところが、いざ中学校で(あるいは小学校の4~5年で)本格的に英語を学び始めると、英語発音に関する限り、途端に雲行きが怪しくなり始めます。まるで内海から、外の荒海に漕ぎ出した小舟のように、それまで波穏やかで、すべて単純明快だった日本語の母音は、いきなり高波を食らってぐらつき、理屈を超えて激しく翻弄されます。と言うのも、一歩英語の世界に足を踏み入れると、ローマ字と日本語の間に存在していた、あの鉄壁の整合性はもはや見当たらず、 a=「ア」という公式は全く通用しないのです。例えば、talk は「タルク」ではなく「トーク」(/tɔ:k/)と発音します。同様に、hall も「ハル」ではなく「ホール」(/hɔ: l/)と発音します。では a=「ア」ではなく、a=「オー」と覚えておけばよいのかと思っていると、face は「ファセ」でも「フォーセ」でもなく、「フェイス」(/feis/)と発音しなくてはなりません。同様に、cake も「カケ」でも「コーケ」でもなく、「ケイク」(/keik/)と発音します。すると、a =「エイ」なのかと思っていると、father は「フォーザー」でも「フェイザー」でもなく、「ファーザー」(/fɑ:ðə/)と発音しなければなりません。では a=「 アー」なのかと思っていると、 cat は「コート」でも「ケイト」でも「カート」でもなく、「キャット」(/kæt/)と発音しなければなりません。何だ、やはり a=「ア」だったかと思うのもつかの間、cut も「カット」(/kʌt/)と発音し、but も「バット」(/bʌt/)と発音します。こうなると u=「ア」という別の公式が成立するのかと思っていると、bat もまた「バット」(/bæt/)です。
4.「ア」音以外の英語母音の難しさ
英語母音の難しさは「ア」音に限りません。そこで、英語の「ア」音以外の母音の難しさにも少し触れておきましょう。母音全体の問題としてとらえる視点が必要だからです。すでに、a =「ア」と言う公式が全く成立しないことを見ましたが、 i =「イ」という公式も英語では成立しません。例えば、kid (子山羊、子供)の発音は「キッド」(/kid/)ですが、kind (親切な)は「キンド」ではなく「カインド」(/kaind/)です。また、hid (hide の過去形)は「ヒッド」ですが、hide (隠す)は「ハイド」(/haid/)です。同様に、u=「ウ」(/u/)という公式も英語では必ずしも成立しません。put は確かに「プット」(/put/)ですが、cute は「クテ」ではなく「キュート」(/kju:t/)であり、cut は「クット」(/kut/)ではなく「カット」(/kʌt/)であり、use は「ウセ」ではなく「ユーズ」(動詞の場合)(/ju:z/)または「ユース」(名詞の場合)(/ju:s/)です。また、e=「エ」という公式も英語では必ずしも成立しません。end は「エンド」(/end/)であり、red も「レッド」(/red/)ですが、Peter の発音は「ぺテル」ではなく、「ピーター」(/pi:tə:/)であり、recede(後退する)の発音は「レセデ」ではなく、「リシード」(/risi:d/)です。同じく、o=「オ」という公式も必ずしも成立しません。lot の発音は「ロット」(/lɔt/)であり、hot も「ホット」(/hɔt/)と発音しますが、lotus(蓮) の発音は「ロトゥス」ではなく、「ロゥタス」(/loutəs/)であり、hotelの発音 は「ホテル」ではなく、「ホゥテル」(/houtel/)と発音します。また、son(息子) の発音は「ソン」ではなく、「サン」(/sʌn/)と発音し、vote (投票する)の発音は「ヴォテ」ではなく「ヴォウト」(/vout/)と発音します。
いかがでしょうか。英語母音の世界は乱れに乱れていると思われませんか。勝手気ままな発音に走り、ルール無視も甚だしいという印象が残りませんか。これだけの混乱ないし混迷を前にして、自分は英語の発音に自信がある、英語の発音で迷ったことは一度もない、と言い切れる日本人が、果たして何人いるでしょうか。勿論、日本の英語教育では、多くの基本単語の読み方を、ALTを含めて、学校でしっかり教えますから、よく使われる日常語のうち、1000語程度なら、ほとんどの中学生がかなり正確に発音できるようになります。しかし、それは原則的に、テスト前の丸暗記などを奨励する類の教え方です。また、丸暗記と言えば、日本の受験生は、大学入試までに、4000~5000語かそれ以上の英単語をがむしゃらに覚えなけれはならないとされています。これではさすがに受験生の全員が、それらの単語を、発音も含めて、すべて正確に覚えるのは難しいかもしれません。
英語の発音に限って言えば、上に見た a 音に典型的に見られるように、英語のスペリングと発音がなかなか一致しないところに重大な問題が隠れています。中学生が、初めて見る単語を、スペリング通りに音読しようとすると、二度に一度は発音を間違える可能性があります。すると、先生から間違いを指摘され、頻繁に間違えると、叱責すらされかねません。これでは堪りません。この不条理に、何年たっても振り回される言い知れぬもどかしさ、悔しさ、そして敗北感は、本当に何とかならないものでしょうか。
5.スペリング通りに読めない英語の現実
ここで、頭を冷やすために、少し視点を変えてみましょう。ネイティブの英語話者たちはこの事実をどう思ってるのでしょうか。彼らにとっても厄介な問題ではないのでしょうか。実態としては、彼らは特に意に介してはいないように見えます。英語がスペリング通りには発音できない言語であることを、特段、苦にはしていないのです。彼らにしてみれば、それは生まれたときから聞き知っている母語であり、そこに、一定程度、音とスペリングの非対応が見られる、という比較的マイナーなことがらであって、それで日常生活に何らかの重大な支障が出るわけではないからです。
ただ、彼らにとっても、英語を話すことに比べると、英語を読む(文字を見てそれを正しく音読する)ことはかなり難しいのも事実です。そこで、「読み書き」は学校で丁寧に、きちんと、学ぶ必要があるのです。そして、一方で、読書の必要性は、日本人の場合と全く変わりません。読書の素養がなければ、多くの難しい言葉を使いこなせませんし、契約書も、取扱説明書も、何が書いてあるのか分からず、新聞記事さえ読めないからです。そこで彼らは、小学校に入学すると同時に、日本語の五十音に相当するフォニックスを使って、スペリングと発音の関係を必死で覚え、五年、十年という長い年月をかけて、ついに相当難しい単語を含む英文でもしっかり読みこなし、正しく音読することができるようになります。つまり、書かれた英語を読むことの重要性を、その難しさと共に、ネイティブの英語話者の多くがフォニックスの学びと読書を通じて理解し、また身をもって体験するのです。実は、ここに、私たち日本人にとっても、英語音読、並びに英語読解の訓練を経て、名著を含め、成熟した英文を数多く読みこなすという、英語学習上の、極めて真っ当、かつ高度な目標を立て、それを達成していく上で、大いに役立つヒントが潜んでいるのです。
6.解決の糸口としての、発音効率という仮説
A. a+t の場合
でも、当面の目標は英語の音声面の問題点の克服です。私の考えでは、英語母音の実態に即した学びを実践するなら、英語発音の完全制覇に向けた一連の訓練を、すぐにも開始することが出来ます。そして、そのとき、私たちがまず押さえておかなくてはならないのは、日本語とローマ字の見事な一致を確かめたときの、あの五つの母音に対応する五つのアルファベット( a, e, i, o, u )の中の、例えば a なら a を、英語を学ぶ際には、「原母音 a の発音を担う一個のアルファベット」としてのみ眺めるのではなく、「アルファベットa と共起する他のアルファベットとの関連」を重視する必要があるということです。なぜなら、アルファベット a は、単体としては何物も語らず、五個の「ア」音への変化(へんげ)の可能性を秘めつつ、a をそのスペリングの一部に含む語としてのみ、すなわち、個々の、独特のアルファベット結晶体としてのみ、存在しているからです。
これは、実は、フォニックス(phonics)的な発想です。つまり、発音の法則性を見つけるには、私たちの当面のターゲットであるアルファベット a が、それを含む、どのようなアルファベット集合、すなわち、「どのような単語のスペリング」(個々の英単語を構成する、およそ 2~16個ほどのアルファベットの、単語ごとの取り合わせと個性的な配列)の中で使われているかを、見る必要があるのです。単語をスペリング通りに読めないことにいら立ち、その理不尽を告発する前に、アルファベットの特異な集合体である個々の単語のスペリングこそ、弁別的発音の様々なヴァリエーションを正確無比に仕分けし、独自のシグナルを放っている英語発音の司令塔である、という認識が不可欠なのです。
そこで、浮上してくるキーワードは、私たちの内で、無意識のレベルで作動しているあるシステム、すなわち、特定の子音(もしくは子音群)と原母音 a (母音 a が五種類の「ア」音に分化する前の音を想定し、私がその音を原母音 a と名付けました)との間に見られる、一種の発音効率の法則です。例えば、「原母音 a+t 」という連携的繋がりの中では、原母音 a はなぜか、「ア」と「エ」との中間の音として実体化します。この音は、現行の発音記号で記すなら/æ/ で表わされる音です。ただし、この音が出現するのは、「原母音a+t」を含む単音節語の中、もしくは「原母音a+t」を含む多音節語の 中で、原母音 a を担うアルファベットa に、強勢アクセントが来る場合に限ります。例を挙げてみましょう。
cat, hat, mat, sat, fat, rat, pat, that, at, batter, latter, patter, scatter, attitude など。
cat から at までの語はすべて単音節語であることに注意してください。また、batter からattitude に至る五個の多音節語に出現する a 音には、必ず強勢アクセントが来ていることを辞書で確かめてください。他方、強勢アクセントの来ない「 原母音 a+t 」はどうなるかというと、その時の原母音 a は、他の音節に強勢アクセントがあるため、自信と張りと大音量を失い、エネルギーの燃え滓のような、萎えた曖昧母音/ə/に変わります。例を挙げれば、attire, attribute, formative, talkative などがそれです。
ところで、興味深いことに、上に挙げた単音節語のうち、that と at は、それぞれ接続詞や前置詞として、本来の機能を果たす場合には、その発音は速やかにルーティーン化し、音声ボリュームは可能最小値にまで減衰し、絶対弛緩の象徴である曖昧母音に変わります。次の二つの例文中のイタリック体で示したthat とat を見てください。
1. It is not that I am angry with you.... (僕は別に、君に怒っているんじゃないんだ・・・。)
2. It was at that moment that I realized....(そのときだよ、僕が~だと分かったのは・・・。)
上の1、及び2の文には強調構文が使われています。この構文の接続詞として 使われている that(2では二番目のthat が接続詞)には、上に述べた理由によって曖昧母音 /ə/ が使われます。しかし、これらの文は、すでに述べたように、強調構文 であるため、ゴチック体で示した not とthat に意味上の強調アクセントが生じています(訳文参照)。ですから、2の文の最初の thatは、強調構文の枠組みである接続詞の that ではなく、「あの~」というように、人や物を指す、指示代名詞であり、「まさにそのときだった・・・」というように「とき」を強調します。このようなとき、英語では /æ/ の音が使われます。
B. a +p の場合
次に、a+p も同様に「ア」と「エ」の中間の音/æ/ になります。例を挙げてみましょう。
cap, sap, lap, happen, map, nap, apple, slap, trap, perhaps, capture など。
ただし、apartment や appear は a+p であっても、a+p が構成する音節に強勢アクセントが乗らないため、音のボリュームが減衰し、相対的に委縮して、原母音 a の音は、曖昧母音、すなわち、/ə/という音になって出現します。
C. a+他の子音の場合
同様のことは、単音節語の場合、または多音節語で、a に強勢アクセントが来る場合には、多くの他の子音(l, f, d, n, m, r, sなど)についても起こります。例えば、
altitude, ally, after, add, animate, amateur, Amazon, Arabic, ass, asphalt
などがその例です。しかし、多音節語に出現した a に強勢アクセントが来ない場合は、B の場合と同じ理由で、曖昧母音に変わります。例えば、
alight, allude, afraid, admire, another, amaze, among, arise, assembly, associate, astonish
などがその例です。
これに対して、ll で終わる単音節語では、a は、先ほど見たように/ɔ:/ と発音します。all, ball, call, hall, tall, fall, gall などがその例です。また、lk やld やltで終わる単音節語でも、 /ɔ:/の音になります。例えば、talk, walk, balk, bald, halt, asphalt などがそうです。さらに、a+w の結びつきも、/ɔ:/の音になります。 例えば、awful, saw, paw, law, hawk, crawl などがそうです。
D. a +rt、a + rd、a+rk、a +rpの場合
原母音 a が rt , rd, rk, rp などの連続子音と結びついて一語を形成する単音節語の場合には、a の発音はそれらの連続子音の構音イメージに合わせるため、 /ɑ:/もしくは /ɑ:r/(米国発音)となります。理論上、これらの連続子音と結合する際の a の音は、それら連続子音に共通して含まれる子音 r の構音イメージの遡及効果を特に強く受けることが予想されます。そしてその理論上の発音は、実際の発音と一致していることが認められます。次の例を見てください。
art, cart, dart, part, bard, card, hard, dark, lark, mark, market, carp, harp, carpenter
E. 原母音 a の五分化
日本語やローマ字ですでにその例を見たように、「原母音 a」 は、人類が、それぞれのコミュニティーの内部で、多くの聴覚的弁別が可能な語を生み出すことで、コミュニケーション能力を発達させていったある時点で、五つに分化したものと思われます。すなわち、日本語の「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」、ラテン語の a, e, i, o, u がそれに相当します。これらの五つの母音は、口の開き方によって、開いた音から閉じた音への段階的変化がまず認められます。「ア」は一番開いた音で、次に半分閉じた音「エ」、最後にもっと閉じた音「イ」が生まれました。他方、口の後ろで出す二つの音が生まれました。口を丸めて開き、舌を後ろに引いて出す音が「オ」で、口をしっかりすぼめ、舌を後ろに引いて出す音が「ウ」です。舌の位置と口の開き具合の、五通りの組み合わせによって、聴覚的に区別される五つの基本母音が、こうして生じました。
F. 先行する母音を曖昧化させる "r" の力
ところが、英語では、ラテン語のa, e, i, o, u という五つの母音が、後ろに来る子音が r の場合、その多くが長音の曖昧母音に変化します。例えば、i+r では、/ir/ ではなく、/ə:/ に変化します。かくして、bird, firm, stir, などがご存じのような発音になるのです。e+r も/er/ではなく、/ə:/ に変化します。例えば、perhaps, super, carpenter, certainly, perfect, alert, driver などがこれに該当します。また、 u+r でも/ur/ ではなく、/ə:/ に変化します。たとえば、purchase, disturbance, lurk, surface, furniture などがこれに該当します。/ə:/ は注意を要する発音です。i+r でも、u+r でも同様の音に変化しているところが味噌です。r という子音の構音イメージが強烈なので、舌は前にも後ろに行かず、中間に保たれたのです。おなじ曖昧母音でも、/ə:/ は r 由来の母音であって、強勢アクセントを受け入れることができます。本来の曖昧母音 /ə/ は、これに対して音のボリュームが極度に小さく、短い音です。発音練習メニューにおいても、この両者は区別して扱われなければなりません。
7.日本語との比較から見えてくる発音効率の原理
さて、ここで、発音効率という概念について、その輪郭をきちんと説明しておかなければなりません。発音効率は、私が日本人向けの発音指導において使うために作り出した作業仮説で、およそ次のことを指します。
すでに多くの方がご承知のように、日本語では、「子音+母音」の結びつきが、語形成および発音の基礎になりますが、英語では逆に「子音+母音+子音」が、多くの語の形成、並びに発音の基礎になります。英語の特色は、「母音+子音」で終わる語が圧倒的に多いということです。例えば、後者の典型例であるa +t の場合、かなり多くの事例があります。たとえば、at, cat, sat, hat, bat, mat, rat, pat, fat などがそうです。そこで 私は、次のような仮説が成立するのではないかと考えています。つまり、この特定の音素の組み合わせが多くの日常語に出現し、何度も使われているうちに、発音が、原母音 a から 子音 t に移る際に、その到達目的地である t の音が必ずそこに待ち構えていることが強く意識され始めます。そこで話者は、原母音 a の音を早めに切り上げて、子音の t の発音に取りかからなければ、音のバトンタッチがスムーズにいかないと憂慮し始めます。つまり、この特定の音素の組み合わせが頻出するにつれ、発話者の意識の中で、原母音a から t 音に向けて効率よく安全に到達する最短コースの構音イメージが強化されると考えられます。そこで、本来ならば「ア」と発音すべきアルファベット a に対応する原母音 a は、子音 t の強化された構音イメージの影響下に置かれることになり、到達先の 子音 t が発生させる一種の「構音圧力」を受けるのです。言い換えれば、子音 t の強力なイメージ化による構音圧力は、遡及して、原音 a の質を変化させるのです。
もう一つの典型例である a+ll の場合を考えてみましょう。上に見たように、all やball や call など、非常によく使われる基本語がこの組み合わせを持っています。これらの語の発音は、それぞれ、/ɔ:l/、/bɔ:l/、/kɔ:l/ です。では、a と ll が結びつくとなぜ、 a は/æ/ ではなく、 /ɔ:/ と発音されるのでしょうか。発音変化の暗示は、おそらく l の繰り返し、もしくは l+k、 l+d、l +t、l+f という結合にあり、これらの複数の子音で締めくくられる単音節語に限って、このルールが適用されます。 l が一個の場合と二個の場合では、a の発音が異なるところが味噌です。例えば、Calfornia はカリフォルニア州のことですが、発音は /kæləfɔ:rnjə/ です。 この語には l+f の組み合わせが見られますが、語の全体はこの組み合わせでは終わらず、ornia という音が続いて一語を形成しています。つまり多音節語です。これに対して、calfと言う別の語では、発音は /kɑ:f/ です。このことから、llや、ldや、ltで終わる単音節語では、a は/ɔ:/ と発音され、lf で終わる単音節語では a は /ɑ:/ と発音されることが分かります。
なぜそうなるのでしょうか。まず、ll で終わる単音節語の場合には、発音の上でも、 ll と文字を二重にしてまで注意を喚起した子音 l の発音、すなわち、 /l/ の音のイメージが膨れ上がり、原母音 a にまで遡及する構音圧力となって働き、原母音 a を、/ɔ:/ で表わされる音に変化させたのです。lf で終わる calf の場合には、最後の子音は/ l/ ではなく、/f/ です。/f/ の音は、/l/ の音に比べて、口の開き方が少なく、/p/や/t/ の音にある程度近いことを、自分の口で確かめてください。そこで 舌の位置が/ɔ/ と/æ/ の中間である /ɑ:/ に落ち着いたと考えられます。なお、アメリカ英語では、calf を /kæf/ と発音することが、一つの参考になります。
少し難しい話になりました。似たような日本語の例を挙げて説明してみましょう。例えば、現代でもよく使われる言葉の一つに「大変だ」という日本語があります。「大」は「タイ」と発音され、発音記号を使うと、/tai/と表記することができます。ところが、この言葉が習慣化し、発音効率の原理が働くようになると、「タイ」が「テー」(/te:/)に変わることがあります。テレビ時代劇の捕り物シリーズなどによく出てくる下っ端の岡っ引きが「てーへんだ―」と叫びながら、親分に事件を報告する場面などがすぐに思い浮かびます。また、同じく時代劇で、しつこく何かを迫る手下に、親分が「大概にしないか。」というべきところを、「てーげーにしねーか」と𠮟りつける場面も思い浮かびます。ここでは、/taigai/ が /te:ge:/ に変わるのです。これらの日本語は今ではあまり使われず、品も決してよくないかも知れませんが、幾つかの英単語に働いているのと同じ原理に基づく音の変化が看て取れます。あるいは、私の生まれた地方では、方言による訛りによって、「大根」が「デーコ」と発音されたり、「太鼓」が「テーコ」と発音されるのを子供の頃に聞いた記憶があります。訛りの生じる原理の一つは、やはり発音効率の最適化という原理だったのかもしれません。
発音効率という考え方を適用すれば、英語の母音の変化や変容の見方が変わるかもしれません。ランダムで変幻自在に見える母音の変化も、実は英語の特性に応じて、発音を簡便化するのに最も理に適った変化が生まれ、それが一地方で方言として定着したとも考えられるのです。
では、ここで、曖昧母音 /ə/ の役割と、それがどのようにして生まれたかを、次に推理します。
8.曖昧母音 /ə/の存在意義
曖昧母音は英語の発音において、恐らく、最も注目度の低い母音です。英語の教育現場でさえ、きちんと注意を向ける人はそれほど多くはありません。けれども、英語における曖昧母音は決して過小評価の対象になってはいけません。と言うのも、曖昧母音のおかげで、英語はあの素晴らしいリズムを刻むことができるのです。なぜでしょうか。それは、英語という言語が、強勢アクセントを持つ言語だからです。そして、強勢アクセントが来るたびに、話者は緊張し、それが過ぎ去ると話者の緊張は緩みます。このように、英語話者は緊張と弛緩の間を行き来し、そのことによって、脈動する言葉のリズムを刻んでいるのです。したがって、弛緩を受け入れる曖昧母音は、リズムの脈動を支える心臓のような役割を果たしているのです。それが存在することによって、話者は安心して、原母音 a のボリュームを最小限に落とすことができ、そのことによって浮いた身体エネルギーを、他の母音をより鮮明にする作業に振り向けることが可能になります。
そもそも、人間が一息の間に発することのできる言葉の数はそれほど多くはありません。したがって、できるだけ多くの情報を、効率よくそこに詰め込むことが出来なければ、言葉の戦いに負けます。また、肝心の言葉を明確に相手に届けなければ、説得も出来ず、交渉も成り立ちません。人を説得するには、言葉にメリハリをつけることが必要です。そのためには、間の取り方に注意し、休むときは休みつつも、ここぞというときは一段と声を張り上げる、などの工夫が必要なのです。これらレトリカルな工夫の弁論的実践をを可能にするのが、曖昧母音の存在であり、強勢アクセントの存在なのです。
曖昧母音は、所与の母音の配列を変えるのではなく、すでにある母音配列に発音効率的なメリハリを付けることを可能にする素晴らしい装置です。例えば、investigation の発音は、発音記号では/investəgeiʃən/ と表記されます。音節で区切って表記すれば、in-ves-ti-ga-tion となり、アクセントは ga に置かれます。注目したいのは、ti とtion です。本来、ti は/ti/ と発音するのが普通であり、例えば、 tissue は /tiʃu:/ と発音されます。ところが、investigation では ti は上に記した発音記号でお分かりのように、発音は /tə/ となっています。また、tion も、本来なら、ドイツ語やフランス語がそうであるように、「ティオン」もしくは「ツィオーン」と発音したいところを、曖昧母音を使って /ʃən/ と曖昧化しています。 invesigation では、ga に強勢アクセントを許す代わりに、ti や tion では母音のボリュームを絞りこむことで代償を払わせ、エネルギー消費量を差し引きゼロにしたのです。
他の例で言えば、equate の発音は /ikweit/ ですが、adequate の発音は /ædikwət/ です。前者は ate に強勢アクセントが来ますが、後者ではad に強勢アクセントが来るため、ate は弱音節となり、発音は /eit/ ではなく、/ət/ に変わったのです。そして、こういったことはこれらの単語のレベルだけでなく、文章のレベルでも起こっており、詩やドラマや演説、また日常会話で、恒常的に起こっていることなのです。
9. 発音記号 /ɑ/および /ʌ/ の「ア」音について
多くの方がすでに気づかれているように、英語には「エ」に近い「ア」音 /æ/の他に、「オ」に近い「ア」音 /ɑ/があります。例えば、car, card, father, park, lark, far, hard, mark, garden など、誰でもよく知っている身近な語に使われる英語母音です。ただし、これら語に出現するのは長母音の /ɑ:/ ばかりです。これに対して、アメリカ発音でGod に言及するときには /gɑd/ と発音します。「オ」に近い短母音の「ア」音なので、イギリス発音の /gɔd/ と同じく、この音を聞いた人には「神」と言う意味がすぐに伝わります。この音の発音は、口を大きく開けて、舌を後ろに引き、喉の奥から大きく「ア」音を出します。この母音を持つ語は、ほかにもodd, cod, hot, lot, pot, mob, Bob, mom などがあります。
次に /ʌ/ の「ア」音について 見ていきましょう。/ʌ/ の音は、「オ」と「ア」の中間の口になって音を出すと出る音です。日本語にはない音です。この音は、次に挙げる三種類のアルファベット(群)に対応します。次の例を見てください。
"u" に対する/ʌ/ 音の例:up, us, ultra, umbrella, upon, umpire, undo, ultimate, utter, usher, sun, hunter, cut, hut, lust, crust, rupture
"o" に対する/ʌ/ 音の例:one, son, done, some, other, another, thoroughly, wonder
"ou" に対する/ʌ/ 音の例 :country, couple, famous, tremendous, trouble, prosperous,